友達の山本幹雄校長先生が神保町まで来てくれました。久しぶりの再会です。話が弾みました。
お昼を御一緒して,さぼうるへ。それから,神田明神へ。
神田明神には算額があるというので,山本先生と一緒に行ってきました。
神田明神は,孔子廟のある湯島聖堂のすぐそばにあります。
境内に入ると,結婚式の最中でした。笙や笛に先導されつつ新郎新婦が厳かに歩いています。
見守る人たちの輪に入り,それから算額さがしです。
どこに飾られているのか知らないので,境内を一周しました。
それでも見つからず,社務所で教えてもらいました。
飾ってあったのは,現代の算額4点。その中の1問を読んでみましたが,気の遠くなるような問題で,考えることとストップしました。
江戸時代の数学家が境内で腕を競っていた時代の風に,ほんの少しですがあたることができました。
これを学習する頃の子ども達。
学力格差も非常に大きくなっています。
入試の勉強をしている子にとっては基本問題であり,割合がイマイチだった子にはかなり高いハードルとなります。
そういう学力格差があっても,しっかり指導をしていくのが先生なので,先生という仕事は本当に大変な仕事なのです。
分かる子には一層の理解を深め,イマイチの子には一つず納得できるように。
そういうことが教材には求められてきます。
そんなことを思いつつ,このソフトを作っています。
画面の左側にボタンが幾つもあります。
1つクリックすると,図がちょこっと出てきます。
関連する問題文も赤文字になるので,「問題と図の対応」が分かりやすいです。
一番大事なところは,20分かかる場合は,1当たりでは「全体の1/20」になることです。
30分は1/30になります。
それを感覚的に把握できるように,アニメーションも使って印象づけるようにしています。
3問チャレンジして,「文章問題は面白ね」となってくれれば,ありがたいなと思っています。
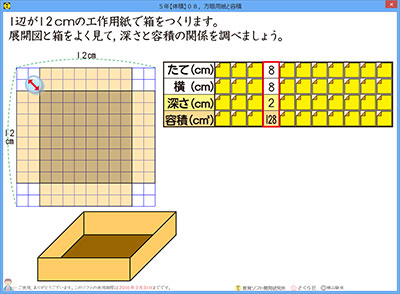 友達の千葉先生のブログを時々読みに行っています。
友達の千葉先生のブログを時々読みに行っています。
授業の様子が中心になっている,真面目なブログです。
そのブログに,算数ソフトの事が記事になっていました。
千葉先生の奥様が5年生の担任で,奥様にダウンロードしたソフトを見せたら,大絶賛だったそうです。
これだけで,充分に嬉しいニュースです。
その上,千葉先生は次のように書かれています。
=========
直感的に分かる
=========
これからの算数授業のキーワードではないか
さすがだなと感じます。
「直感的に分かる」という状態がつくれるということは,「見ている内に,数理的きまり(原理)に自ら気づく」ということです。
自分で気がつくのですから,これは面白いです。
ハッとひらめくのです。
この瞬間は,たまらない面白さがあります。
スカッと爽やか! という感じです。
これが,毎時間のように出てきたら・・・・
算数そのものが好きなっていきますよね。
そうあって欲しいです。
4年生の角のソフトをこの春に作りました。
城ヶ崎先生とのコラボソフトです。
チーム算数で,こんなソフトが・・とのやりとりがあり,そこから生まれた「角の大きさ」のソフトです。
城ヶ崎先生も授業で使いましたが,奥田先生も使いました。
奥田先生の感想です。
--
最高です。
(1)三角定規とは何かがわかる。
(2)1組の三角定規を重ねたときの角の大きさがよくわかる。
動き、最高。
(3)二等辺三角形の2つの角が等しいことがよくわかる
(4)正三角形の3つの角が等しいことがよくわかる
どのソフトも、すばらしいです。
--
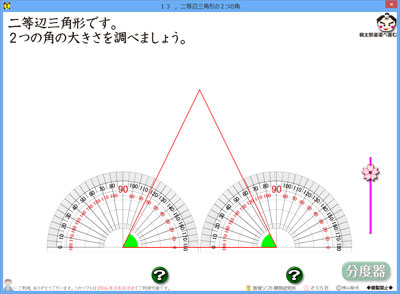 コラボソフトは,かなり的を射たソフトになることが,このことからも分かります。
コラボソフトは,かなり的を射たソフトになることが,このことからも分かります。
医学の世界では,「名医+名薬」のコンビネーションがしっかりしています。
医学の足元にも及びませんが,「名先生+名教材」のコンビネーションで多いに前進して行きたいと思っています。
6年生の文章問題のソフトを開発しています。
割合の考え方を利用して解いていく問題です。
そういう説明的な言葉より,「仕事算」ですと言った方がわかりやすいかもしれません。
この問題は,仕事算の基礎的な問題です。基礎的過ぎて,仕事算らしさ,つまり「単位時間当たりで考える」という思考法が使われていないのです。
使われているのは,「全体と部分」の見方です。
考え方としては,16分,12分,12分と3つの「時間」が出てきますが,これを一旦,「割合」の世界に落とします。それから,再び「時間」の世界に戻るという流れになります。
そういう解き方が分かるように,ちょっと図に工夫をしました。
第1問目では「詳しい線分図」で,非常にわかりやすく表現されて出てきます。
第2問目は「簡単な線分図」なります。シンプルな図でも意味は同じ事を理解します。
第3問目は「もっと簡単な線分図」になります。
問題事に,どんどん簡単になるので,自分で図を書くときには,もっとシンプルにしたいと思う子がでてくれたら,それは嬉しいところです。
完成はもうすぐです。
その次は,いわゆる「仕事算」のソフト開発に入りたいと思っています。

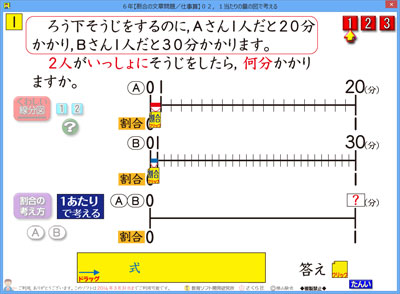
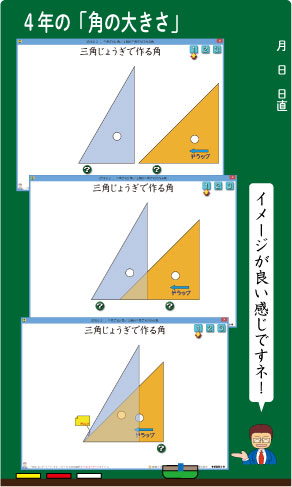
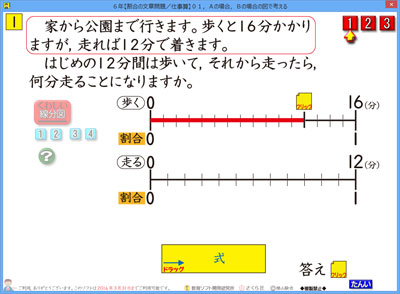
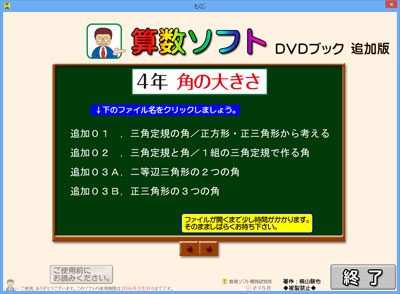
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















