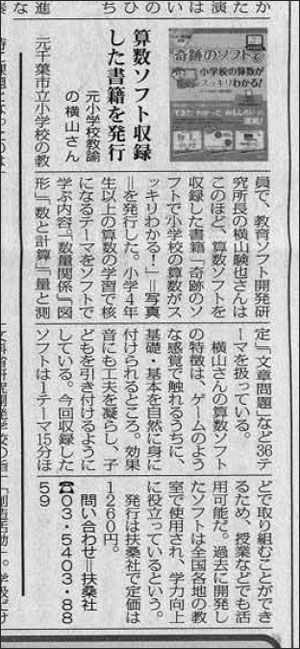 日本教育新聞の1月20日号に,『CD-ROM付き[奇跡のソフト]で小学校の算数がスッキリわかる!』が紹介されました。
日本教育新聞の1月20日号に,『CD-ROM付き[奇跡のソフト]で小学校の算数がスッキリわかる!』が紹介されました。
ありがたいです!
嬉しいです!
とくに,嬉しく思ったのは,ソフトの特徴が記されていたことです。
「ゲームのような感覚で触れるうちに,基礎・基本を自然に見つけられるところ」
「効果音にも工夫を凝らし,子どもを引き付けるようにしている」
ゲームのような感覚,というのは,何度もやってしまいたくなるということです。楽しいからです。
何度もやると,
1,理解場面では,算数のきまりの発見
2,練習場面では,すいすい出来る力をもつ
ことになります。良いことです!
先日,算数ソフトに関係する会議がありました。
私はいつものようにクラウドを映し出して,「こんなソフトです」と紹介しました。
会議ですから,ある目的を持って話し合いをするのですが,途中から「我が家の子が3年生で・・・」と,家庭教育の話しになってしまいました。
ソフトを見て,「算数で一番大事な理解が,これならわかる!」と思われたからです。
日本教育新聞の記事を読んで,あの時の会議の様子を思い出しました。
とても良い記事にしていただきました。ありがとうございます!!
--
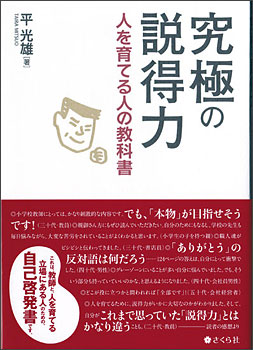 『究極の説得力』の平光雄先生から,嬉しいメールが届きました。
『究極の説得力』の平光雄先生から,嬉しいメールが届きました。
プロスキーヤーの角皆優人氏のブログに,この本が紹介されているとのことです。
こちらです。教育界以外の方が御紹介くださるなんて,『究極の説得力』のパワーはさすがです。
また,指揮者の三澤洋史氏のブログにも紹介されているとのことでした。
こちらです。
このブログはちょっと変わっています。上の方を汽車が走っています。そこを見ると,平先生のことが書かれています。
--
木更津の平野先生からも嬉しいメールが届きました。
若い先生方を集めて,第1回目の学習会を開くそうです。
12月に開催された多田先生の祝賀会で,平野先生と雑談をしました。
その時,平野先生の心がグイッと熱くなったようで,「学習会を開いてみる」と言い出したのです。
その情熱が若い先生方に伝わり,第1回目の学習会開催へとなりました。
30日だそうです。
良いですよね。こういう情熱。
参加する先生方は,レポート持参となっています。
このスタイルは力が付きますね。応援しています!
--
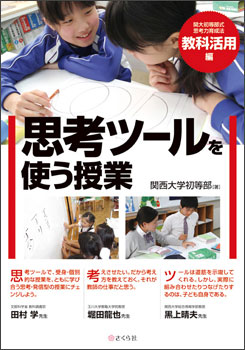 思考ツールの第3弾『思考ツールを使う授業』(関西大学初等部著)がアマゾンに出て,予約受付中となりました。
思考ツールの第3弾『思考ツールを使う授業』(関西大学初等部著)がアマゾンに出て,予約受付中となりました。
『関大初等部式 思考力育成法』
『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉』
この2冊に続く,第3弾です。
思考ツールで3年目。
最初の本が出たときに4年生だった子ども達が,今年いよいよ卒業を迎える6年生になっています。
思考ツールの活用でどう育っていったか,2月1日の公開研究会でその姿を見てみたいです。しかしながら,当日参加できません。残念!
公開の日は,島原先生と合流して感想を語り合う予定でした。
島原先生とは別の機会にお会いして,あれこれお話を伺いたいと思っています。
この『思考ツールを使う授業』は,公開研究会の日に,全国に先駆けて会場で先行販売されます。
もうすでに満員御礼と聞いています。
公開の日に手にできる先生,いいですね!!
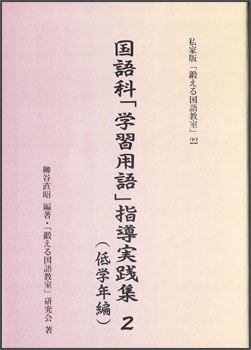 北海道の柳谷直明校長先生が編集されている『私家版「鍛える国語教室」22 国語科「学習用語」指導実践集2(低学年編)』です。
北海道の柳谷直明校長先生が編集されている『私家版「鍛える国語教室」22 国語科「学習用語」指導実践集2(低学年編)』です。
タイトルにあるように,「学習用語」に強い焦点を当てた授業実践が12本も掲載されています。
例えば,太田先生の論文。学習用語として,「話題」「構成」「小段落」「大段落」「要約」「要旨」「立場」「発言」「根拠」などが載っています。意図的にこういう用語を学習させていくのですから,力がつきますね。
12本それぞれが「現状の問題点」→「打開の方策」を示しています。この形は実によいです。読み手として,ちょっと本気になって読んでしまいます。こちらの気合いが高まるので,読めば読むほど勉強になります。
柳谷先生はズバズバ書いています。痛快です。
大谷先生の「平仮名指導系統図」はハッとさせられ,おおいに勉強になりました。この図を参考に,自分ならこうすると考えてみる先生が出て欲しいですね。「大谷図」を超えて進む先生は誰でしょう。
神話が1本入っていました。「国生み」の所で,1年生への授業です。1年生の子に神話。これだけで,十分に学習の意義があります。
子ども達がかなり興味を持ったようで,そういうことがよくわかる良い内容です。
気になったのは,塩。どうも,漢字に振られています。
もしかしたら,参考にした書籍に注釈がなかったのかもしれません。
話は変わりますが,「国生み」のすぐ後には,イザナギとイザナミが結婚する場面が出てきます。
ここの場面,作法的には,「左優先」の古来日本人の思想が学べます。
また,「順番を守る」「ダメだったら,逆にしてみる」といった思考法が,日本人古来の思考方法なんだと哲学することもできる場面です。
古事記や日本書紀は,こういう古来のあれこれを考えさせてくれるありがたい書です。
 中村健一先生の新刊『つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法』(黎明書房)です。
中村健一先生の新刊『つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法』(黎明書房)です。
まあ,面白いタイトルですね。
このタイトル,真面目に読むと意味が逆転しそうです。
真面目な国語の先生は,このタイトルを真剣に読まない方が良いでしょう。
第1章は「授業の最初に教室のムードを支配する」です。
「教室のムードを支配する」という考えは,いいですね。
これができると,「開放」も支配できるようになるからです。
第2章もいいですよね。「テンポさえ良ければ子どもたちは授業に乗ってくる」
少し早口なぐらいで話すと良いことがしっかり書かれています。
若い先生は中村先生ぐらいのスピード感がいいです。(実際に御本人の講演を拝聴してみてください。絶妙のスピードです。中村先生の口調はお勧めです)
ベテランになったら,福山憲市先生ぐらいのスピード感がいいです。
それより遅いと,厳しいでしょうね。
こんな風に書くと,「そうか,速ければ良いんだ」と勘違いする人がでてきそうです。
テンポ良く話ができる。この状態を作るには,何かが必要となります。
頭の中に話すべき内容が密度濃く入っていることです。
知らないことを,テンポよく話すことは不可能です。
聞き手より,遙かに詳しく知っているから,軽快に話すことができるのです。
中村先生が軽快に話せるのは,ほんとうにあれこれよく知っているからです。
平素から勉強家であるのが中村先生なのです。
その上での妙味が,第2章にたっぷり書かれています。
第3章は,いよいよ授業!という内容です。「授業への全員参加を保障せよ!」
これもいいですね。
ここに書いてあることを,臨機応変に使えるようになるといいです。
新人を教育する立場にある先生は,この第3章を若い先生にみっちり教えてほしいです。
次は,「普通の授業を質の高い授業に変えてしまう方法」を期待しましょう。
その時には,算数編で「算数ソフトを使うべし!」とビシッと決めてもらえるとうれしいです。
昨日の記事が,このブログのちょうど1000ページ目となっていました。
ちょっと前には,1000号になったら,何か特別な記事を・・・と思った事もありましたが,そういうことにはあまり強い意識がないのか,すっかり忘れていました。
--
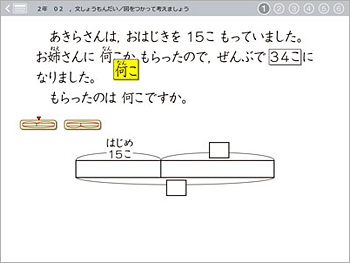 2年生の「図で考える」ところの2本目のソフトが,いよいよできあがってきました。
2年生の「図で考える」ところの2本目のソフトが,いよいよできあがってきました。
文章問題を良く読み,テープ図に数を入れていくことをメインとしたソフトです。
6問も入っているので,1本目と2本目を合わせて使えば,かなりの子が教科書の問題も良い感じで進めると思います。
このソフトも,クラウドにアップします。
冬休み中にはアップできそうです。良かったです。
--
ところで,平先生の『究極の説得力 人を育てる人の教科書』です。
今日,名古屋でこの本の出版記念講演が開催されました。私は仕事があって行くことができなかったのですが,参加された方々は100名前後もいらっしゃったようです。それも,民間の企業の方々です。
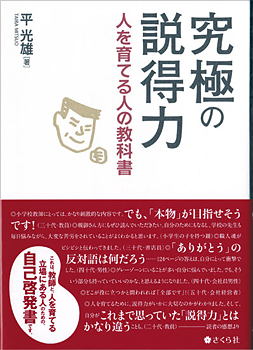 平先生は,名古屋で人生を教えるような活動もされていて,人望が非常に厚く,このような記念講演の開催となったそうです。
平先生は,名古屋で人生を教えるような活動もされていて,人望が非常に厚く,このような記念講演の開催となったそうです。
第一章の第一。
若い先生が,何度も言っているのに,係活動がうまくいかない・・・とぼやいています。
それに,平先生は言い方に問題があるのでは?と言うのですが,若い先生は,そんなことはありませんとこたえます。
この後です。
平先生の重みのある一言が,出てきます。
その後,その一言の心の内の解説が出てきます。
この話しが実に良いのです。納得感が高いです。
平先生の話が,民間の方々の心にも響く理由もよく分かります。
先生という職業は,人を育てる仕事そのものですから,どの先生でも,それなりに人を育てる力を持っています。
その考え方が,同僚の先生方を超えて,一般社会の方々にも響いているのが,平先生です。
帯に書かれている感想は,
・三十代の書店員。
・四十代の会社員。
・五十代の会社経営者。
・二十代の先生。
すごいですよね。
先生に限らず,人を育てる立場にある方々には,読んでいただきたいなと思います。
--
郵便受けに本が3冊届いていました。
金曜も土曜も確認しなかったので,あらあら,という感じでした。
机の上にこの3冊を積むのですが,まだ,順番待ちの本が1冊あるので,4冊重ねになりました。
それを横目に,今夜は,『菊と刀』の続きを読みましょう。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















