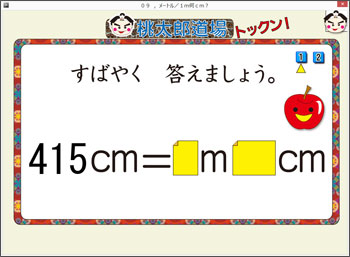 2年生の「長さ」のソフトが進んでいます。
2年生の「長さ」のソフトが進んでいます。
1ページ目,2ページ目の他に,桃太郎道場を取り付けました。
桃太郎道場では,換算の特訓をします。
152cmが1m53cmと理解していますので,その先は機械的にじゃんじゃん練習します。
その「じゃんじゃん練習」が実に簡単にできます。
りんごをクリックすればいいのです。
そうして,「5m!95cm!」と答えればOKです。
これを繰り返すだけで,「じゃんじゃん練習」できます。
【算数ナレッジ】
長さの学習をするとき,「コピー物差し」をつくると楽しく勉強できます。
作り方は簡単です。
ものさしを何回かコピーして,それを切り取り,のりでつなぎます。
2mか3mぐらいになるまでの長さで作っておきます。
そのままにしておくと,何かの拍子に切れてしまうので,巻き尺のように丸めておきます。
それを持って,あちこちの寸法を実際に測る活動をします。
「コピー物差し」は紙なので,書き込みができます。
「私の身長 1m43cm(143cm)」「大木の周囲 1m52cm(152cm)」・・・・
そうして,実際に幾つか計ったら,だんだん目分量で長さの検討がつき始めてきます。
長さの計測学習の大事な点は2つ。
1,正確に計る
2,目測できる
2の「目測」部分の練習になるのが,次の勉強です。
「1m以上のところは,10cm間隔に1つずつ記録を書き込みましょう!」といった勉強をします。
こうすることで,「1m20cm~30cmの間はどれかな」と周囲を探すようになります。
これが見当を付けてから計る学習になり,目測力を高めます。
良い感じで勉強したら,最後は壁に貼り付けて,しばし鑑賞をしましょう。
--
算数ソフト,完成したらクラウドにアップします。お楽しみに!
複式学級の担任をしている奥田先生から,嬉しいメールが届きました。
--
<成績もよかった>
4年 分数(平均点94点)、 調べ方と整理の仕方(平均点98点)
--
複式学級ですから,指導を十分に行ったとしても,普通の学級のようには行き届きません。
それで,この成果です。
算数ソフトを使うだけでなく,ソフト画面を印刷し,そこにコメントを入れて教室に掲示しているそうです。
PCでの学習は,電源を落としてしまうと見ることができません。
そこをしっかり補う方法です。なるほどと感心しています。
近々,第4回 和歌山県教育実践研究大会が開催されるそうです。
それに向けて,パネル3枚分の掲示物を奥田先生が作っています。
その1枚分ほどが算数ソフト関係の掲示物となっているそうです。
奥田先生の力の入れ具合を強く感じます。
大会が成功するよう,祈っています。
--
2年生の「長さ」の単元に,右のソフトを追加する予定です。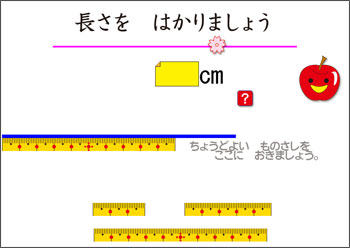
1m~2mの範囲内の
・目盛の読み方
・単位の換算
を学ぶことができます。
特に,125cmが1m25cmになる単位の換算は,重要な学習になります。
間違えやすいのは,10mm=1cmを学んでいるので,つい,10cmが1mと勘違いする子が出ることです。
そこを,難無く通過できて欲しいと思い,これを作り込んでいます。
完成は,まだ先ですが,できあがり次第,クラウドにアップしていきます。
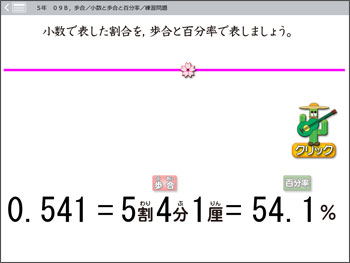 藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。
藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。
5年生の割合の中に,「小数」と「歩合」と「百分率」の変換の学習をします。
「小数」と「百分率」は,学校でも多めに勉強しますので,何とかなりやすいのですが,「歩合」はちょっと厳しいです。銀行の利息も今や百分率の%です。残っているのは,野球の打率ぐらいのように思います。
日常感覚が薄いものは,多めに練習をしないと身につきません。
そんなことも考えたのでしょうか,藤本先生は,「09B,歩合/小数と歩合と百分率/練習問題」を使いました。
クリックして問題に答えていく学習もしましたが,小数・歩合・百分率の表記がよくわかる学習もしました。
それは,右のように答えが出たままの状態で,桜スライダーを左右に動かすことです。
すると,スライダーの動きに合わせて,小数・歩合・百分率が同時に変わります。
これを見たら,相互の関係がかなりつかみやすくなります。
メールが嬉しかったのは,この学習をしたら,子ども達が「画面に釘付け」になったと書いてあったからです。
「釘付け」ですよ。
算数で,子ども達を釘付けにさせることは,なかなかできません。
集中が高まっているので,子ども達は自分なりに,「換算のきまり」を見つけていったと思います。
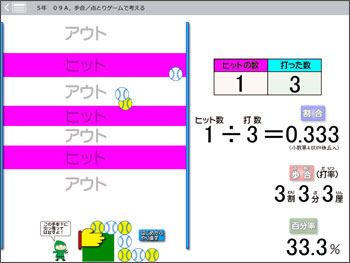 「09B」の前に,「09A」があります。
「09B」の前に,「09A」があります。
ご覧の手打ち野球ソフトになっています。
1回打つ毎に,打率は変わります。
そこで,打つ度に,割合→歩合→百分率を答える仕組みに作ってあります。
藤本先生は,この面白さを味わってもらおうと,コンピュータルームで一人一人が楽しめるように学習をされたそうです。
御家庭でもクラウドを使う方がいらっしゃいます。
5年生で割合を学習したら,このソフトはぜひ使ってもらいたいです。
--
三重県の坂野先生から,嬉しいメールが届きました。
学生時代から情報教育を学んで来ており,パワポやフラッシュなどを使って教材用ソフトを作っています。
その坂野先生が算数ソフトを使い,感想を送ってくれました。
「効果がすぐに表れて、私も子どもたちも驚きです」
ソフトを喜んでもらえ,学習効果が出たことも嬉しいですのが,もっと嬉しいのは,坂野先生がまだ二十代の若者い先生だと言うことです。
自作の教材ソフト作り,これに算数ソフトを加えているのです。
これから先,たっくさんの子ども達の算数力を救ってくれます。
そう思うと,嬉しくてなりません。いつか,お会いしたい先生になりました。
--
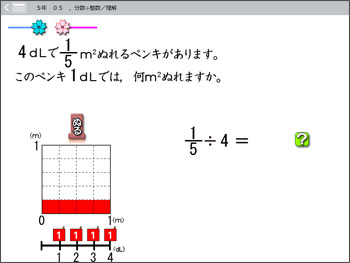 算数ソフトのクラウドに5年生の「分数÷整数」のソフトを3本アップしました。
算数ソフトのクラウドに5年生の「分数÷整数」のソフトを3本アップしました。
05 ,分数÷整数/理解
06 ,分数÷整数/練習/真分数・仮分数
07 ,分数÷整数/練習/帯分数
右は,「05」の理解のソフトです。
4dLが1dLになるのですから,÷4になり,それは図の赤が4つ分から1つ分に減ることを意味します。
そこをアニメーションで見ることができるので,÷4の意味がかなりわかりやすくなっています。
一番の学習所は,「÷4すると,分数の分母が増える!」ということがわかることです。
その理解には,青桜スライダーです。
これを左右にドラッグすると,縦の仕切りが変わるので,「ああ,なるほどね」となりやすいのです。
クラウドにアップしましたので,まずは,ご覧になって楽しんでみてください。
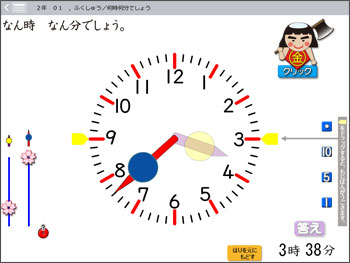 嬉しいメールをいただきました。
嬉しいメールをいただきました。
特別支援学級の指導で有名な上原淑枝先生からです。
時計のソフトの左端に,さくらスライダーが2つセットされています。
さくらを下に降ろすと,針が次第に消えていきます。上に上げると,針ははっきり見えるようになります。
これが「針を意識するのに良い」とメールをいただきました。子ども達と授業をして,子ども達の意識が針に集中したのです。
針を見て何時何分か答える勉強をするとき,片方の針が見えなかったら,「見せて!」「見たいです!」と強く願ってきます。消えている針を見ないことには,答えられないからです。
こういう場面作りをすると,子ども達の集中も高まりますね。
上原先生のクラスのお子さんが針を意識したのですから,「正答したい!」という強い願望が心にわき上がってきた子とわかります。こういう子は,もっとやりたいと願ってきます。それが積み重なって伸びていきます。
上原先生のように,「正答したい!」という心を引き出す学習が日々連続したら,学ぶ子も,親御さんも喜びますね。
この時計のソフトもクラウドの1年,2年に入っています。
--
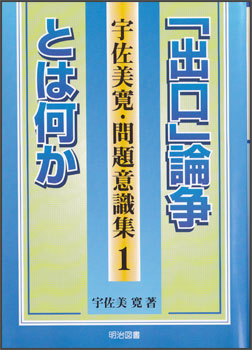 嬉しい気持ちになって,宇佐美先生の本を読みました。『「出口」論争とは何か』(明治図書)です。
嬉しい気持ちになって,宇佐美先生の本を読みました。『「出口」論争とは何か』(明治図書)です。
戦後最大の教育論争と言われている「出口」論争が詳しく書かれています。
『論理的思考』(メヂカルフレンド社)で一文の書き方を学びました。
この本では文章の書き方を学べます。
どうして÷9の「9」が分母の方に来るのかは,理解の場面となります。それ用のソフトは,このソフトとは別に1本作ってあります。
そうした学習をして,いよいよ理解したことを習得するために,何問か練習をしていきます。
このソフトは,その練習用のソフトです。
練習をするとき,分母に「×9」ともってくることは,さほど難しくありません。
昨日も書きましたが,経験ある教師が気にするのは,約分です。
約分をすることはわかっていても,スッキリ約分ができない子がいます。
高校生の時,担任の先生が時々,覚えるまでの話しをしてくれました。
--
単純なことは3回もやれば覚えるものだ。
でも,人によってはこれが13回ということもある。
どちらにしろ,覚えるに必要な回数はさほど多くない。
しかし,ちょっと複雑なものになると,3回ではすまなくなる。
2倍3倍はかかる。とはいえ10回前後もやれば大丈夫だ。
覚えるのが苦手な人は,残念ながら13回の数倍を必要とする。
何かしらの策があれば,それを使うもいい。
策がなければ,根気を働かせることだ。
100回はやると覚悟を決めれば,何とかなる。
高が100回だ。
--
分数の計算。
もし,約分をしなくても良いのなら,3回コースです。覚えの悪い人でも13回で覚えられます。
しかし,約分をするのは,お約束です。避けて通れません。
「100問問題集で気合いを入れてやりましょう」と話して,その気になっても,結果は思うに任せません。
算数が苦手な子には,このいい話より,目の前の複雑感が勝ってくるからです。
途中で嫌気がさしてきます。
算数に向かっていく100回ではなく,算数から心が離れていく100回になってしまいます。
そういう子でも,このソフトは効果的に働きます。
なぜでしょう。
約分するかしないかに,エネルギーを集中できる設計になっているからです。
ごらんのように,二者択一です。
この形は正答したくなります。自然と数に着目をします。
約分の規則性を自分で把握する場となっているのです。
近々,クラウドにアップする予定です。5年生の先生,ぜひ御活用ください。
約分はもう教えやすい所になりました。
--
城ヶ崎先生との座談クラブ。
ちょっと予定が入り,2月1日(土)になりました。

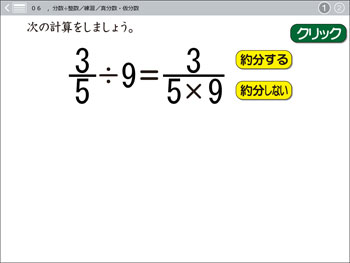
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















