野口塾で,幼稚園関係の先生方とお話をする機会がありました。
最初は,姿勢の話だったのですが,途中から算数の話題になりました。
そうして,久々にいい感じの質問を受けました。
「幼稚園の時にやっておくべき算数は何ですか」
私の答えは,ずっと前から決まっていたので,なかなかいい質問だと思いつつ,お話をしました。
答えは簡単で,「指折り30まで数えられる」です。
このことを,ミッドナイトのスーパーホテル部で話したら,叱り方の専門家・中嶋郁雄先生が強く反応していました。
理解してもらえたようです。
ただ,これはPCの無い時代の私の答えです。
算数ソフトが,ipadなどで使える時代に入ったら,どうなっていくのでしょう。
それなりに,楽しみな世界と感じています。
--
たまたま,ベクターシェイプで立体を作っていたら,急に,体積ソフトも作り直したくなって,あれこれやってみました。
そうしたら,なかなか良い感じになってきたのです。
ベクターシェイプでソフトを作ると,かなり手間がかかります。でも,うまいこと山を越えれば,操作性のいいソフトになります。
ご覧のように,立体の中の1段を抜き取るということもマウスで簡単にできます。
5年生では,「たて×横×高さ」を学ぶのですが,すぐ上の6年生では「底面積×高さ」を学びます。
そこへのつながりも十分にもてる良い作りになっています。
--
今月中までには完成させて,DLマーケットの5年体積セットをアップデートしたいと思います。
上手くアップデート出来れば,5年の体積をダウンロード購入された皆さんに通知が届きます。
そうしたら,アップデート新作をダウンロードして使うことが出来ますね。
ありがたい仕組みです。
分数の分母と分子の間にある線の名称。
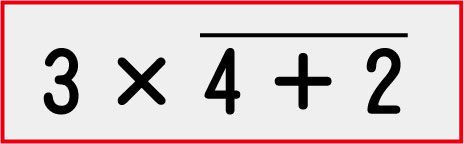 坪田耕三先生からお話を伺ったときに,「括線」ではないかと教えていただきました。
坪田耕三先生からお話を伺ったときに,「括線」ではないかと教えていただきました。
ヨーロッパで図のような線が括弧の変わりに使われてた時代があり,それが明治になり日本に輸入され,その呼び名が括線だったのです。
「括」は「括(くく)る」という意味ですから,線の及ぶここからここまでを括って一つに見なしますよ,という意味になります。
分数はそれが上下になったものですので,この線の及ぶ上下を一つに見なすことなので,括線なのではないかということでした。
非常に説得力があり,その後,私もそれなりに調べたのですが,分数の線の名称は出てきませんでした。
ということで,暫定「括線」ということで頭を落ち着けました。
ところが,ところが。
ジャパンナレッジで「分数」を調べたのです。
結構なヒットがあり,上からザザッと目を通したら,最後の方に「分数線」とでていました。
何だろうと思い中を読んだら,中国語で分母と分子の間の線のことを「分数線」というです。
発音は,フェンスウ シェンという感じです。
分数線という呼び名が,中国のいつの時代から使われていたのかは分かりませんが,ストレートな感じで好感を持ちました。
括線は意味を表す言い方。
分数線はストレートな言い方。
横棒は見た目の言い方。
こんな風に把握するのが良いのかなと思っています。
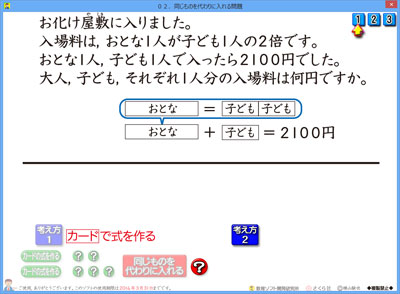 5年生の文章問題のソフトです。
5年生の文章問題のソフトです。
去年度作ったのですが,そのまますっかり忘れていて,ずっとハードディスクの中で眠っていました。
今日,藤本先生からコラボのメールをいただき,ハッと思い出し,ハードディスクの中らか救い出しました。
このソフトは,代入の考え方を学べるソフトです。
ちょうど,代入する直前までのところのソフト画面をキャプチャーしたのが,右の画像です。
赤い?ボタンをクリックすると,代入が始まります。
その様子を見れば,代入ってこういうことか!と伝わります。
考え方2の方は,それを線分図で見ることができます。
嬉しいのは文章問題が3問も載っていることです。
類題を3問行えば,たいていはやり方がわかってきます。
望ましい状態になりますね。
--
山中伸之先生の『キーワードでひく小学校通知表所見辞典(CD-ROM付)―ぱっと開いてすぐ書ける1973文例』が大人気です。お友達の先生にも,ぜひお知らせください!
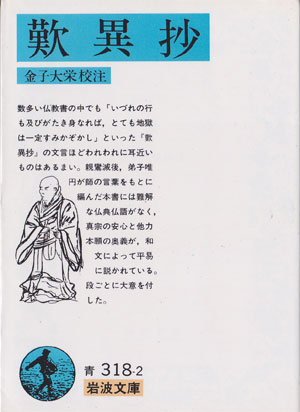 『歎異抄』にも,分数が登場していました。
『歎異抄』にも,分数が登場していました。
1回目に読んだときには,スルーしていたのですが,2回目には,「オオッ!」です。
「古親鸞の仰せごと候ひし趣,百分が一つ,かたはしばかりをもおもひでまゐらせて,書きつけ候ふなり。」
最初,この「百分が一つ」を「万が一」と同様の意味と思ったのですが,どうも,前後からすると,違うようです。「ほんの少しでも」という意味として取った方が通じやすく感じます。
そうだとすると,とても珍しい分数の使い方となります。
私にとっては,分数活用の新種発見です。
親鸞(1173~1262年)は鎌倉時代の前半の方です。
ほぼ同じ頃の人に,鴨長明(1155~1216年)が『方丈記』を書き記しています。
こちらにも,分数が出ています。
鴨長明の使い方は,広さの表し方として,分数を使っています。
都のうち三分が一焼けたとか,家の広さが十分が一になったとか。
思うに,この頃,分数は舶来の高級な概念だったのでしょう。
日常で使うほどではなく,学問した人同士では通じる言葉だったのだろうと思います。
習った人には,簡潔に表現できる,かなり気の利いた概念だったのだと思います。
--
歎異抄,岩波文庫からも1冊購入しました。
やっぱり,親鸞となると勉強しようという気持ちが強くなります。
分数で楽しみましたが,仏教の教えを日常生活に活かすには「滅」を意識するのが一番と感じています。
そうすると,私の好きな言葉,「そういう事もありますよ」に行き着きます。
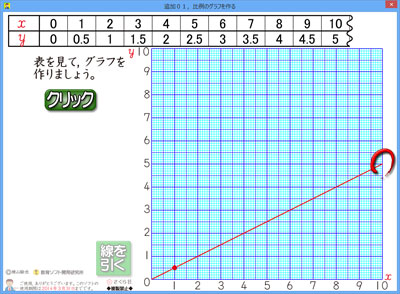 6年生の比例のグラフのソフトです。
6年生の比例のグラフのソフトです。
このソフトを,もっと算数にアップしました。
しばらく,アップさしておく予定です。
6年生のご指導をされている先生,ぜひ,ご覧になってください。
このソフトは,妙に面白いです。
表を見ながら,「ここぞ!」と思う1点を方眼紙の上でクリックします。
外すと,何事も起こりませんせん。
その瞬間,あれっ?と思って,表を見てしまいます。
それから,あっ!と思って,クリックしてしまいます。
外すと,正答したい!という気持ちが高まるんですね。
ちょっとした,学習意欲づけになりますね。
右の場合,x=1のときのy=0.5です。わざわざ(1,0.5)をクリックしなくても,もっとわかりやすい(2,1)をクリックすればよかったのですが,これは私の学生時代の習い癖です。
このソフトでわかってほしいことは,比例のグラフは1点が決まれば,「原点→1点」をつなげばOKということです。
それを見ている内に感じ取れるような作りにしてあります。

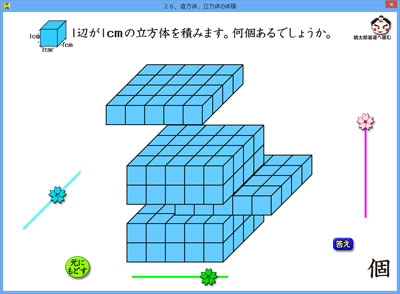
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















