「第2回 奇跡の算数セミナー」を7月27日(土)に開催します。
会場として,水道橋駅近くの会議場をお借りしました。
20名で満員となる部屋を借りましたが,PCなどを設置しますので,どう考えても18名様までの入室となりそうです。
ベトナムへ行く前に,kyositu.comニュースやフェイスブックでお知らせしました。
早速,参加希望のメールが届き,残席はわずかに4席となりました。
参加ご希望の先生,御連絡をお急ぎください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第2回 奇跡の算数セミナー
~「見れば分かる算数」からの出発~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遅れると取り戻しが難しい算数。
その算数に,今,異変が起こっています。
手を挙げることの無かったあの子が,急に手を挙げはじめた。
「明日も算数ある?」と,算数を楽しみにする子が出た。
遅れていた子が,「見ている内に分かった!」と言い出す現象が起
こっているのです。
しかも,ある日1日だけそうなるのではありません。
毎日のように続きます。
このような授業はどのようにして生まれるのか。
それから,どう指導を進めたらよいのか。
「第2回 奇跡の算数セミナー」では,その実践やヒントを提案し
ます。
──────────────────────────────
※日程や内容は変更になることがあります。
1 日時
7月27日(土)14:00~18:00
2 場所
内海(うつみ)3F
東京都千代田区三崎町3-6-15
http://www.kaigishitsu.co.jp/
3 参加可能人数
18名限定
4 日程
13:30~ 受付
14:00~14:10
趣旨説明————————–
14:10~14:30
第1講座 理論編
「子どもが算数を理解するということ」—-横山験也(千
14:30~16:50
第2講座 実践編
「見ているだけで力が付く算数指導1 回数にこだわれ!」
————–佐々木智光(千葉県)
「見ているだけで力が付く算数指導2 力の向け所はここだ!
————–城ヶ崎滋雄(千葉県)
「複式学級で実現した自学自習システム/その準備と計画」
—————-奥田吉彦(和歌山県)
「学力向上推進教員のデジタルとアナログの融合指導」
—————-藤本浩行(山口県)
「U30が巻き起こす,マネジメント式算数指導」
————–佐藤宗巧(神奈川県)
17:00~17:30
第3講座 算数ソフト最前線
「2学期に向かってGO!」—————
17:30~
閉会—————————-
5 参加費
2000円
6 申込先
横山験也 yo◆kennya.jp (◆を小文字の@に
(以下を電子メールでお知らせください)
1参加者氏名:
2勤 務 校:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ハノイとハロン湾の観光旅行に行ってきました。
行く前に,愛知の村井先生から,「ハノイ・ハロン湾」の観光記録を見せていただきました。
ドアの付いていないジープに乗り,激しく揺れて,植物の枝がビシバシと・・・・。
それなりの覚悟ができたので,現地に行って驚きました。ハロン湾が世界遺産に認定されたこともあり,道路がどんどん良くなっているそうです。ですので,揺れは厳しくなく,道も広く,快適に行くことができました。

ハロン湾への道中,線路と平行する所があったのですが,ごらんのような有様です。夕方になると,家の中が暑いので夕涼みに線路の上に座る光景は当たり前だそうです。
その線路ですが,商店の真ん前も,気にすることなく敷かれています。鉄道は,こういう事で良いのだろうかと思ったのですが,こちらでは良いのです。
 こういう文化の違いを感じると,やっぱり日本は良いなと思います。何が,良いかというと,何から何まで良いなと感じます。
こういう文化の違いを感じると,やっぱり日本は良いなと思います。何が,良いかというと,何から何まで良いなと感じます。
オートバイの量が半端じゃないことは,知識で知っていましたが,実際に見ると驚いてしまいます。
ハノイの市内の信号待ち,その最前列は全車線がオートバイ状態です。
バスの上から見ていたら,バイク同士の接触がありました。ぶつけられたと感じた方がなにやら言葉を発したのですが,そのまま,両者走り続けて,行ってしまいました。通行人が接触するのと似たような感触なのだろうなと思った次第です。
このツアーの名称は「びっくりベトナム・・・・」というのですが,もっとビックリしたことは,野口先生と同じ部屋に泊まる旅行だったのです。ですので,成田に集合してから,成田で解散するまで,ずーーーっと,御一緒でした。
当然,話しは無駄話が多くなります。これが,大きな勉強になりました。
旅から戻った今,さらに精進せねばと思っています。
明日からベトナムです。研究や研修ではありません。ツアーの観光旅行です。
誘ってくださったのは野口芳宏先生です。
ですので,中身はかなり濃くなります。
その前日の今日,ディレクターの3Dについて,プロの方とお話ししました。
どうも,算数の立体には良い感じのようなのです。
赤青の3Dメガネを掛ければ,そこに良い感じで立体が登場するようなのです。
その3Dメガネですが,紙製なら100円ぐらいで手に入ります。
もしかしたら,立体の授業中に3Dメガネを掛けて「オーッ!」と声を出しながら授業をするクラスも出てくるかもしれません。
それを研究授業でやったら,参観された先生方も,子ども達より3D立体に目を奪われるかもしれません。
2000年前後の頃から,こういう近未来的な授業がいつかできる日が来ると思っていました。
また,そういう授業に,強いあこがれを持っていました。
なぜなら,算数そのものの魅力で,子どもたちを魅了できるからです。
元来,算数は魅力の固まりのような教科なのですが,紙や黒板に描くという形でしか示せなかったので,その魅力が90%ぐらい眠ったままなのです。
ソフトを作ることで,算数の魅力をかなり発揮できるようにはなったのですが,まだ,70%ぐらいは寝ていると思っています。まだまだ多いに研究の余地があります。
どうやら算数は進化を始めたようだと考えるぐらいがちょうどよいですね。
校内研の通年の講師を引き受けています。
その小学校へ行ってきました。
今回は,「算数ソフトの紹介」です。
『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』全30巻の中から,適時選び,どんなソフトがあるのか,紹介しました。
そうして,最後の10分ほどは各学年で自由にソフトを見ていただきました。
今回の校内研,たぶん,全国的にも珍しい形と思います。
授業で使いたいソフトがなかったら,私の方でできるだけ準備していくという形で進むからです。
指導をする先生と,教材を開発する人とが力を合わせる感じの校内研になります。
この形は,今,算数好きにするMLで藤本先生や奥田先生達と実際に行っています。
それを校内研でも体験できます。
私にとっても,ありがたい研究となります。
帰り際,6年の先生と6月に授業するところを話し合いました。
「倍と割合」の所になりそうです。
指導案検討の日が近いようなので,早めにソフト開発をしてみたいと思っています。
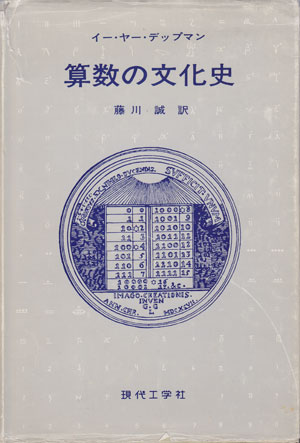 神田の古本屋街をぶらっと歩くとき,のぞいてみたくなるのが明倫館さんです。理工系の専門的古書店です。
神田の古本屋街をぶらっと歩くとき,のぞいてみたくなるのが明倫館さんです。理工系の専門的古書店です。
明倫館さんの棚には,算数など初等数学関係のコーナーがあります。そこに,今日はどんな新着本が並んでいるか楽しみに見に行きます。
右の『算数の文化史』を発見した時は,タイトルにオッ!と来ました。
パラパラっとめくって,調査研究書とわかったので,購入しました。
論説書も面白いのですが,調べて書いてある本も格別いいです。
興味深かったのは,インカの記数法です。
写真が載っていました。沖縄の記数法とそっくりなのです。
インカと沖縄が結びついてしまったので,頭の中は「へー」です。
しばし,その写真を見つつ,これはどういうことなのだろうと,あれこれ想像を巡らしました。
そうして,気がついたことは,「数の記録は身の回りにある物を使う過程を通る」ということです。
とりあえず,ここで充分OKです。
数年後には,これが少し前進するかもしれません。その時が楽しみです。
また,5×5までのかけ算ができれば,残りの九九は指で計算できることものっていました。それも,紀元前から行われていたそうです。フランスのオーベルニュ地方で行われていたことは,森毅先生の本で知っていたのですが,まさか,紀元前からあったとは思いも寄りませんでした。
これで,オーベルニュ地方の指計算は,「生きる化石的存在」となりました。
私の頭の中の算数史が変わりました。
ちょっと色物的なことも載っていました。
西洋で13をなぜ嫌うかです。
原因は算数にあったのです。
デップマン先生のおかげで,「13=不吉」は都市伝説となりました。
ほるぷ出版の「3D 日本地図めいろ」が来月発売になります。
児童書をたくさん手がけてきましたが,3Dは今回が初めてです。
ですので,今,ちょっと3Dがマイブームになっています。
いままで気にもしていなかったのですが,ディレクター12のサイトを見て,ビックリしました。
「高度な3Dゲームの制作」とドーンと書かれているのです。
これまでも,何度かディレクターのサイトを見てはいたのですが,3Dへの興味がなかったので,ずっとスルーしていました。
ネットで調べたら,どうも,紙の赤青の3Dメガネでも立体視ができるようなのです。
見るための3Dメガネは簡単に手にはいるとして,作るのは難しいのだろうなと思います。
それも,アドビのサイトに出ていました。
どうも,「_movie.stereoscopyParallaxDiff=20」と命令を書き込む程度のことで,奥行きが設定されるようなのです。
もし,これだけでOKなら,これは簡単です。
この20をちょっと操れば,出てきたり引っ込んだりと自由自在です。
この出てきたときに,その飛びだし比率に合わせてズームアップするとなると,ちょっとやっかいですが,もし,そうだとしても1行か2行書き加えればいい程度ですみます。
もしかすると,「3D 学習ゲーム」「3D 学習パズル」が作れ,簡単に楽しめる日を迎えられそうです。
今はバタバタとしていて,そういうところのプログラムを勉強している余裕がないのですが,少し時間がとれたら,3Dのプログラムを組み立てて,試作第1号というのを発表してみたいです。
楽しみが増えて,嬉しい限りです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















