 親友の中嶋郁雄先生がビジネス書を出しました!
親友の中嶋郁雄先生がビジネス書を出しました!
『叱って伸ばせる リーダーの心得56』(ダイヤモンド社)です。
野口芳宏先生を師事し,「叱る」という教育的行為に研究の照準を合わせ学び続けていたら,ついに,ビジネス書を書き表すにまで至りました。
中嶋先生のような学びの道。多くの若い先生に見習って欲しいところです。
---
リーダーとして部下から信頼される存在になるためには,「叱る」という行為は避けて通れません。
心に響く叱り方
叱られたい部下の存在
叱れない上司と叱られたい部下。この溝を何とかして埋めたい。私が本書を執筆するきっかけでした。
---
この本の序章の太字部分です。
読んで,響くものを感じますよね。
続きをぜひお読みいただけたらと思います。
 その中嶋先生が書き表した教育書の一つが『教師の道標 名言・格言から学ぶ教室指導』(さくら社)です。
その中嶋先生が書き表した教育書の一つが『教師の道標 名言・格言から学ぶ教室指導』(さくら社)です。
中嶋先生は教育書としても,ビジネス書の走りのような本をすでに書き表していたのです。
実践の節々に役立つ金言・格言が実践と共に,分かり易くガッツリ記されています。
こちらもお勧めです。
---
関連記事:
今日,今年初の忘年会メールが届きました。
山中伸之先生からです。
野口先生・山中先生と,毎年,忘年会を開催しています。
いつも,12月も押し迫った頃です。
それも,野口先生が御講演先から東京へ夕方お戻りになる日です。
極めて限定的な日程で開催されるのですが,今年もやりましょうという方向でいます!
「天意重夕陽 人間貴晩晴」
野口先生が講座で時々お話下さる言葉です。
天が夕日を重んじるように,人間も晩年を晴れやかに貴びたいものです。
一年過ごせば,時として卑しい気持ちになることもあります。
野口先生,山中先生との忘年会で,その不浄を清め,晩晴に向けて歩みたいと思います。
--
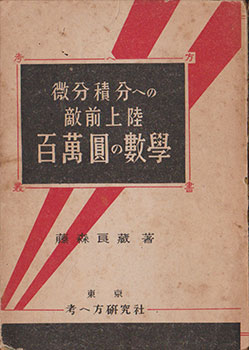 そんな良い気分になったメールを開く時,ちょうど,この本を読んでいました。
そんな良い気分になったメールを開く時,ちょうど,この本を読んでいました。
「百万円」なんて書いてある本です。ちょっと,まずかったかなと思いました。
それにしても,この本,驚きのタイトルですよね。
『微分積分への敵前上陸 百万円の数学』です。
若い頃,算数の本として一番面白いと思ったのが藤森良蔵先生の本でした。
算数の考え方の基本中の基本がしっかり書いてあり,驚きを持って学びました。
その藤森先生の微積の本です。
昭和14年の初版発行ですから,戦前の本です。
きな臭い状況だったとしても,微積はどうすると敵前上陸となるのか,まか不思議です。
不思議なのは,タイトルだけではありません。
この本,表紙は横書きなのですが,中は縦書きなのです。
数学書なのに縦書きなのです!
なんともおもしろい作りです。
勉強になるのは,藤森先生独特の比喩表現です。
微積に比喩というのも,なんだか妙な感じなのですが,ある程度の比喩があると,それでスコンと分かることもあるので,なかなか勉強になります。
比喩の得意な城ヶ崎先生がこの本を読んだら,ちょっと面白がるかも知れません。
昔の本なので,ソフト開発には直接的には役に立ちませんが,頭の働きに少し幅ができた感じがしています。
--
関連記事:
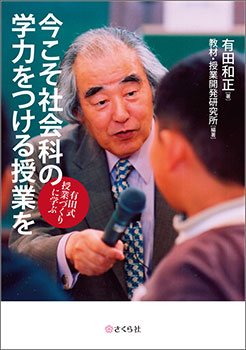 有田和正先生が御生前に御提案下さった本『今こそ社会科の学力をつける授業を--有田式授業づくりに学ぶ』がアマゾンに出ました!!
有田和正先生が御生前に御提案下さった本『今こそ社会科の学力をつける授業を--有田式授業づくりに学ぶ』がアマゾンに出ました!!
半分は有田先生御論文。
半分は,有田先生の御提案を引き継いだ11名の先生方の御論文で構成されています。
「一時間に一回も笑いがない授業をした教師は逮捕する」
有田先生に逮捕されたいです。
「鉛筆の先から煙の出るスピードで書きなさい」
有田先生に煙を見ていただきたいです。
予約をして,本が届くのを楽しみに待っています。
--
小学館さんからも,『人を育てる:有田和正追悼文集』がアマゾンに出ました!
有田先生を追いかけている先生,有田先生から学びたいと考えている先生,ぜひ,両方の本を読まれてみて下さい。
--
そうして,今週の日曜,「有田和正継承セミナー」が東京の四谷で開催されます。
私も一こまお話しさせていただきます。
満員御礼となりましたが,事務局の計らいで定員が10名増えました。ぜひ,お申し込み下さい。
----------
関連記事:
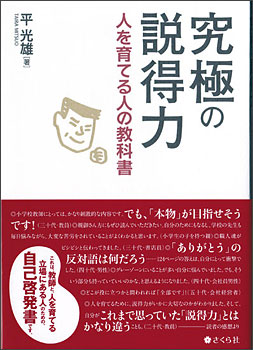 平光雄先生の『究極の説得力』が今ぐんぐん売れています。
平光雄先生の『究極の説得力』が今ぐんぐん売れています。
この間ずっと,アマゾンで在庫切れが続いています。
在庫が無くなるとアマゾンから何冊送って下さいと連絡が来るので,それに従って本を送っています。
送った本がアマゾンに届くと,「在庫あり」とか「5点在庫あり」などと表示されます。
ところが,『究極の説得力』は,届いたその日に,また在庫切れとなってしまいます。
連絡が来て,郵送している間に,注文が入っているのです。
それだけ,この本を求める方が増えているのです。
表紙にも示されていますが,この本は教育書には珍しい「自己啓発書」です。
しっかりした自分作りを行いたいと本気で思っている先生が増えてきているのでしょうね。
いろいろと新しい問題が増えている教育界です。
自分をしっかりさせる修養が,今の時代に求められる大事な事柄となっているのです。
この本の価値を決めているは,「はじめに」に書かれているこの言葉にあると私は思っています。
「説得力は,話の技術だけの問題ではなく,教師の生き方,人間性の問題である」
同じ話をしても,聞き手の心に響くかどうかは,話の技術だけでは決まらないのです。
聞き手の心に響くような人になるよう,自分を磨くことが,遠回りのようでも実は最大の近道なのです。
ちょっと,章立てをご紹介します。
第一章 人を育てる仕事に就いたのだ
1 教師の基本は「与える」精神にあり
2 まず「受け止める」器の大きさが必要なのだ
3 こだわりの学級経営は意外と弱い
4 アドバイスほど安易なものはない
5 土台づくりはスキマ時間に
第二章 つまるところ説得力勝負だ
第三章 人間としての幅と深み
第四章 見た目も磨かねばならない
第五章 「手っ取り早く」はあり得ない
目次を見ても,普通の教育書とは違うことが分かりますよね。
与え方を知るだけでは,不足があるのです。
受け止め方を知るだけでは,不足があるのです。
手っ取り早い方法を知るだけでは,不足があるのです。
何が大事なのか。
その道を歩んだ平先生の人生観・教師観にふれてみると,なるほどと腑に落ちるところが多々出てきます。
人に教える立場の方,自分の話が伝わりにくいと思っている方。
この本,お勧めです!
ぜひ,ご一読ください。
『究極の説得力』←イチ押し!
--
平先生は致知出版から『道徳の話』を出しました。
こちらも,すばらしい内容の本です。
----------
関連記事:
 中嶋郁雄先生の新刊です。
中嶋郁雄先生の新刊です。
『新任3年目までに身につけたい「超」教師術!』(学陽書房)です。
牽引術・経営術・授業術・ダンドリ術・関係術・対応術
この6つの術が詳しく書かれています。
読むと,なかなか濃い話で,3年目でなくても読んで欲しい一冊です。
中嶋先生とは,野口塾が始まった頃から,交友を深めています。
野口塾がスタートし,数年した頃からどんどん本を書くようになりました。
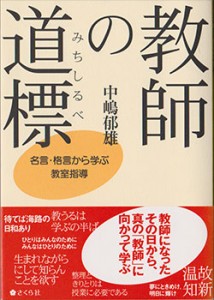 さくら社からも『教師の道標』が出ています。
さくら社からも『教師の道標』が出ています。
中嶋先生は22日(土)に開催される「算数ソフトのセミナー」にも,講師としてお話下さいます。
お子さんが小学校に入学する半年前から,算数ソフトを使って家庭学習をしていました。
そのお子さん,入学前に3桁のたし算・ひき算を暗算で出来るようになりました。
しかも,1日10分15分ぐらいの家庭学習です。
驚きますよね。
お時間のある先生,中嶋先生の家庭学習の話をぜひ聞きに来てください。懇親会では教師術の話も聞くことが出来ますね。
----------
関連記事:

平光雄先生の新刊が致知出版から出ました。
『道徳の話』です。
一枚の紙に,ちょこっと書く。
それを子ども達に見せる。
すると,道徳がしっかり子ども達に伝わります。
ああ,こんな簡単な方法があったのかと得心しました。
算数ソフトを使うと頭にストンと算数が入るように,ちょこっと書いた絵で心にすとんと落ちていく道徳です。
しかも,その一つ一つの徳目も実に良いです。
全国に普及して欲しい道徳です。
家庭でも簡単にできる,質の高い道徳です。
『道徳の話』は,「道徳を子ども達にどう伝えるか」がスッキリと書かれている実に良い本です。
お勧めします。
平先生の著書と言えば,『究極の説得力』があります。
こちらの本では,どんないい話も「誰が伝えるか」で伝わり方が大きく変わります。
語る人はどうあるべきか,教える人はどうあるべきか。
それが説かれています。
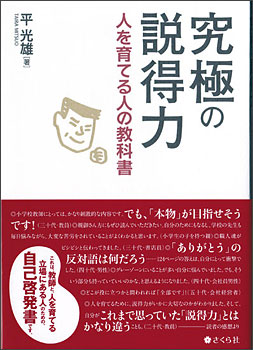 --
--
平先生先生とは,若い頃,教育のセミナーでお会いしたことがありました。
あれから,四半世紀が過ぎ,縁あって,再び交流するようになりました。
久しぶりに会った時,平先生は技術の追究ではなく,人格磨きが重要だと私に話してくれました。
そのダイナミックな生き方が,一つは『究極の説得力』として形になり,一つは,子ども達への『道徳の話』として形になりました。
これから先も,大いに注目していきたい先生です。
皆さん,良い本です。是非,お読み下さい。
---------
関連記事:






![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















