きょうは,嬉しいお知らせを一つ。
有田和正先生の新しい本が来月刊行予定です。
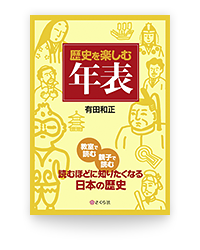 昨年13年の3月に,『歴史を楽しむ年表』を刊行しました。
昨年13年の3月に,『歴史を楽しむ年表』を刊行しました。
「年表と地図の本があったらいいね。
先生も読んで勉強になり,子ども達が手にしても調べたくなるような本があったらいいね。」
筑波大付属小で教鞭を執られていた頃を思い出しつつ,なぜ,年表や地図の本があると良いのか,
お話ししてくださいました。
そうして,この『歴史を楽しむ年表』が生まれました。
元教師の私が読んでも,面白いです。ちょっと語ったり,クイズにしてみたりと,楽しめます。
アマゾンのカスタマーレビュー。
よしドン氏から「内容も抜群。さすが有田先生。小学校で教える機会のある人はぜひ読んでおくべきです」と御高評をいただいています。
すると,来月刊行は「地図」の本なのかと思えてきます。
しかしながら,「地図の本の前に・・・」ということで,有田先生から新しい企画をいただきました。
それが来月に刊行予定です。
さて,どんな本なのでしょうか。
--
関連記事:
 『チャレンジ!学校クロスワード王 プラチナ』(ほるぷ出版)が,おかげさまで増刷になるとの連絡を受けました。
『チャレンジ!学校クロスワード王 プラチナ』(ほるぷ出版)が,おかげさまで増刷になるとの連絡を受けました。
クロスワードは,子ども達に人気がありますね。
3年生を担任していたときのことです。
帰りの会で,市からのお便りを配布しました。
そこに,小さなクロスワードが載っていたのですが,それを見つけた子が鉛筆を取り出してやり始めました。
すると,他の子も次々にやり出し,帰りの会なのかクロスワードの会なのか分からなくなりました。
「やりなさい」と言われてやるのが勉強の一つの形になっています。
「食べなさい」と言われて食べる野菜と似ていますね。
野菜なら,肉と混ぜ調理すれば,カレーに混ぜて調理すれば・・・とたくさんの知恵が働きます。
勉強にも,そういう知恵を!
そんな事を考えて,若い頃は,学習ゲームをたくさん作りました。
-------
このクロスワードの答えを,ノートに書くと,「上下左右の位置関係を把握する勉強が出来る」と,塚田先生が教えてくれました。なるほど!と感心しています。

--
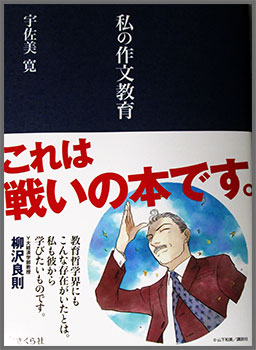 電車に乗る用事がありました。
電車に乗る用事がありました。
今日は,『私の作文教育』を選び,鞄へ。
「粗大な(おおざっぱな)印象による感想を書かせてはならない。小さい箇所まで見える読みかた,疑問の理由が自覚できる読みかたをさせるための作文なのである。」(p66)
傍線を引き,二重丸を書きました。
納得する内容が次々に出てくるので,電車が降りる駅に付き,ドアが開いてあわてて下車ということになりました。
車中で本を読んでいると,途中でちょっと眠くなってくることがあります。そんなときは,無理をすることなく,軽く眠るようにしています。
『私の作文教育』は,そういうことが必要ありません。
--
ウキに私の名前がありました。
誰が書き込んでくれたのだろうかと思いめぐらすと,思い当たる人が浮かんできます。
でも,本当にその人かどうかは,わかりません。
どなたかわかりませんが,私のことを気にしてくれた方だということは,確かです。
感謝しています。
 日本教育新聞に,『しごこちのいい学校』(鎌田富夫著)が紹介されました!!
日本教育新聞に,『しごこちのいい学校』(鎌田富夫著)が紹介されました!!
掲載された紙面は別冊のようについてくる「週刊教育資料」8月25日号の「BOOK」のコーナーです。
記事を書いた方は,元川崎市立小学校校長・北村清氏です。
北村氏は,最後の段落で次のように記しています。
--
まさに「しごこちのいい学校」づくりの楽しさを物語るすてきな話ではないか。学校づくりに腐心している人にぜひ薦めたい本である。
--
この本の記事の下に,もう一冊紹介されています。
『池上彰の「日本の教育」がよくわかる本』です。
こちらの記事を書いた方は,飯田稔氏です。若い頃,何度かお会いしたことがあります。
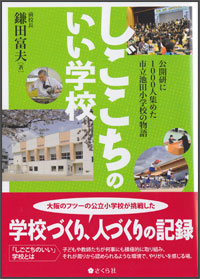 『しごこちのいい学校』が紹介された日本教育新聞は,日本最大の教育新聞です。
『しごこちのいい学校』が紹介された日本教育新聞は,日本最大の教育新聞です。
光栄なことに,若い頃,私もちょっと書かせていただいたことがあります。
また,その頃は教育雑誌にたくさん原稿を書いていたので,日本教育新聞が面白いということを書いたことがありました。
 和歌山の奥田先生が,『奇跡のソフトで 小学校の算数がスッキリわかる』の学習画面一覧を作ってくれました。
和歌山の奥田先生が,『奇跡のソフトで 小学校の算数がスッキリわかる』の学習画面一覧を作ってくれました。
http://www.geocities.jp/y_okkuu/2014/genki-soft.pdf
算数ソフトファンの先生,ぜひ,↑をご覧下さい。
いろいろなソフトが,この本の中に収録されていることがわかります。
かなり,お買い得ですね。
--
さらに,6年の比の学習で使えるソフトの活用例もアップしてくれました。
こちら です。
こういう活動をして下さる奥田先生に感謝です!!
--
この夏は,いつも以上に外出が多く,道中読書が進んでいます。
算数関係の本も読みますが,ちょっと珍しい本を読み返しました。
それは, 三浦つとむの『認識と言語の理論』です。
三浦つとむの『認識と言語の理論』です。
50年ほど前の本です。
学生の頃に学んだ弁証法を,この本からも学びたくて,難しい!と思いながら読んだ,懐かしい本です。
読んでいる途中に,仮説実験授業の庄司和晃先生の「三段階連関理論」が出てきました。
そうでした。庄司先生と三浦氏は仲が良かったんだ!と,あの当時の思いがよみがえりました。
おかげで,頭の中は弁証法でギラギラになりました。
そうして,今日。
認知症などに詳しい社長さんとお会いしました。
簡単な,認識と脳の関係を聞くことができ,勉強になったのですが,聞いている私の頭の中に,三浦つとむや庄司和晃がゆらゆらしています。
次第に、認知症と認識論がどう重なるかが気になってきました。
これは、面白い勉強になりそうで、近いうちに、認知症方面の本を1冊読んでみたいと思いました。
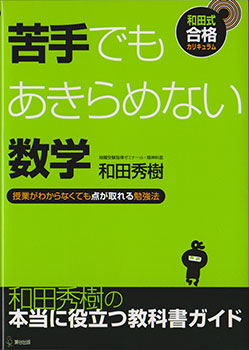 私のことを「横ちゃん」と呼んでいる社長さんの会社が出した数学の学習を効果的に行う本『苦手でも あきらめない 数学』です。
私のことを「横ちゃん」と呼んでいる社長さんの会社が出した数学の学習を効果的に行う本『苦手でも あきらめない 数学』です。
もちろん,受験数学です。
私のテリトリーでは無いのですが,いつか高校数学にもソフトで迫っていきたいので,興味津々で読みました。
「はじめに」のしょっぱなから,グッドでした。
数学苦手の原因が出ています。
なんと,「授業がわからない」です。
この本の後半にも書いてありますが,数学は積み上げの教科です。
小学校・中学校の9年分のツケがたまっていたら,背伸びしたって,こつこつと積み上げてきた子の高さには届きません。
だからといって,その現状で嘆いていても始まりません。
そこから,授業がわかるようにするには・・・となります。
面白いのは,考えるのではなく,「手を動かして」伸びていくというのです。
中を読んでいくと,その理由がよくわかります。
そこを私風に書くと,「図にしろ,式にしろ,リアルに書く」。すると,「それが頭に染みこんで・・・」となるのです。
手での書き込みの多数の事例を見て,「なるほど」と思いました。
さらに,さすがだなと思ったのは,「5分考えても解き方がわからなかった,解答を見なさい」というのです。
これ,まさに極意です。
知らないことは解けないのが普通です。
解けるようにするには,知ることです。知るには,答えを見て考えの道筋を把握することです。
大いに納得をしました。
この本には,数学の事例がたくさん出てきます。
ですが,そこがわからなくても,この本は落ちこぼれた子へどうアプローチし,何をレッスンすればいいのか,わかりやすく書かれています。
気になる子が教室にいる先生,夏休みにこの本を読んでみるのも良いと思います。
ところで,今の算数はソフトが登場したので,高校の数学より学習が進歩しています。
教科書を見る前にソフトを見ておけば,それでグッドになります。
理解がどんどん進み,自力での学習が進められるほどになります。
そこに,この本に書いてある「手を使う図式のノウハウ」を子ども達に伝授したら,どうなるでしょう。
伸びの大きい子が育つように思います。
大いに勉強になった一冊です!
--
スクーで「横山験也の算数の授業」を「受けたい!」という方が11名になりました。楽しみです。
第5回教育の原点セミナーは,9月6日です。私は発表しませんが,なかなか良い感じです。






![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















