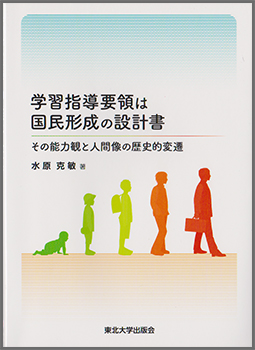 何を思ったか,この本を急に読みたくなり,読みました。
何を思ったか,この本を急に読みたくなり,読みました。
『学習指導要領は国民形成の設計書』です。
明治以降の指導要領の変遷を,通史として学ぶことができます。
これ一冊読めば,かなりわかるので,たぶん大学のテキストではないかと思います。
指導要領変遷のあれこれが書いてあるので,知らないところを確認するときに,この本は便利です。
戦前と戦後。面白かったのは,やっぱり戦前ですね。
特に,教育勅語が出てくるまでは,道徳をどうするかでかなりヒートアップしていたことが書いてあり,なかなか面白かったです。
西洋文明を重視すると道徳軽視となり,世の中の混乱を見ると本来の日本道徳の重視が叫ばれます。そうして,最終的に日本道徳をしっかり教えようとなっていきます。
その近代日本の道徳のはじめの一歩的位置に存在しているのが,西村茂樹氏の『小学修身訓』です。
『小学修身訓』についても,この本には出ていました。
そこを読んだとき,オッ!と思いました。
なぜなら,自分も持っているからです。
作法の研究をしているとき,この本は外せないと思い,神保町の古本屋で買い求めた一品として,今,部屋の本棚に積んであります。
この『小学修身訓』は,教科書です。
それもちょっと変わった教科書です。
児童が声に出して読み上げ,暗唱してけるように作られた教科書なのです。
このスタイル,野口塾に参加している先生は,オッ!と思いますよね。
野口先生の『言葉と作法』が,読み上げることで指導していくスタイルになっています。
青森の駒井先生の「素読指導」も,読み上げる指導です。
さくら社の『日めくり論語』も,日直が読み上げ,クラスがいい感じになっていくと知らされています。
そうして,この読み上げ暗記するスタイルは,文部省が初めて作った道徳教科書『小学修身書』にも引き継がれました。
近代道徳の始まりは,読み上げだったのです。
近代道徳草創期の教科書と,現代の道徳教育の一翼を担っている野口塾の指導法が重なっています。
読み上げる指導は,「不易流行」の不易なのです。
7月26日の野口塾in南平での私の作法の話で,ここのところをちょっとお話しするかもしれません。
興味のある先生,ぜひ足を運ばれてください。
--
 宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンで735位になっていました。
宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンで735位になっていました。
読んで初めてわかる,このド迫力。
教育哲学の本は,元来,こういう文章であるべきなのだと痛感します。
教育学全体の中でも15位に位置していました。
さすがは,宇佐美先生の本です!
--
次回のスクー。
7月27日(日)でほぼ決まりそうです。
話は,前回の続き,分数の話です。
◆分母、分子から古代中国を覗く
◆世阿弥も分数を活用していた
これに,あと2本,お話を加えて,次回のお話にする予定です。
詳しいことは,近いうちに,スクーに発表になります。
スクーの準備で,算数関係の本を探していたら,その棚の隅の方に,『日本料理技術選集 箸の本』がありました。
この本,家のどこかにあるとはわかっているのですが,どこに置いたのか,全くわからなくなり,読みたいときに読めなかった,ウォンテッド本でした。
それが見つかったので,しばし,他のことを取りやめて,この本を読むことにしました。
面白いですね。
元々手づかみだった日本人ですが,中国から箸の文化が輸入され,宮中から次第に全国民へと広がりました。
これは,一大生活改革ですよね。
その上,箸は日本仕様に変化し,箸を使う食事の作法も定式化していきました。
こういうところが,日本人の優れたところと思っています。
ここをもう少しあれこれすると,日本人の大きな組織論へとつながります。
何しろ,日本は2000年も続いている国なのです。
地理的な条件とか,民族的な条件とか,いろいろあっても,これは内部に「しなやか」で「強靱」な組織が形成されていたと考える方が自然です。
バラバラな日本人だったら,2000年も持たなかったでしょう。
このあたりについては,土曜日の流し素麺野口塾で,山中先生や中嶋先生,城ヶ崎先生達と語らいたいと思っています。
この日本の組織論がわかってくると,しなやかで強靱な学級経営の大枠がかなり明確になります。
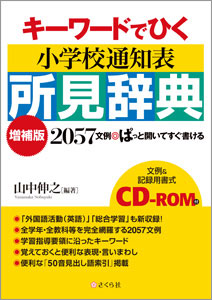 山中先生の『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典 増補版』が,6月16日に発売になりました。
山中先生の『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典 増補版』が,6月16日に発売になりました。
おかげさまで,アマゾンで大好評です。
文例の内容もいいですし,総数も非常に多くなりました。
その上,CDまでついています。
「やっ!これは便利だ」と声が出そうです。
話はそれますが,戦前,『や,此は便利だ』という小百科事典が出版されていました。発売元は平凡社。平凡社の百科といえば,『世界大百科事典』です。私も愛用しています。
その平凡社が,戦前,一番最初に出した百科事典の名前が『や,此は便利だ』なのです。
そのくらい驚きと便利さがある本だということで,山中先生の『所見辞典 増補版』に絡めました。
解説をしなければならない話は普通絡めないのですが,妙に嬉しくて書きました。
--
さて,12日の土曜日ですが,私は「流し素麺野口塾」に参加します。
10時頃から開催され,夜の8時ごろまで続きます。
多く交流して,少し勉強。どちらかというと修養セミナーです。
例年,私は車で参加しています。
稲毛駅で何人か乗せて,野口家へ向かいます。
今回は,次の方々が乗車します。
・中嶋郁雄先生
・城ヶ崎滋雄先生
・算数ソフトを使っている先生
豪華ですよね。
狭い車の中に,このメンバーが乗るのですから,それなら私もぜひ!と思いたくなりますが,車内は満席です。
野口家到着までには,1時間はかかります。
いつもながら,車中話はかなりおもしろくなりそうです。
会場に着けば,山中先生や塚田先生,松澤先生,伊藤先生,神部先生,熊谷先生,平井先生・・・
豪華メンバーが続々とやってきます。
誰と話しても,大いに勉強になります。
流し素麺野口塾は修養的なセミナーなのですが,実践発表の場もあります。
この場で発表できる先生は,高いレベルで幸せ者です。
なにしろ,その場に,出版社の方が例年3社,4社と参加されているのです。
自然,月刊誌に起用されたり,本作り・・・ということも,起こっています。
歓談の時間がとにかくたっぷりある非常に珍しいセミナーです。
詳しくは,こちらです。
今日は,城ヶ崎滋雄先生とチーム算数。
城ヶ崎先生は,開口一番,明日のスクーのことを質問しました。
「2分の1」と「10分の5」は同じで違うというのは,どういうことか??
いろいろと考えたけど,よくわからないとのことでした。
考えてもわからないことはたくさんあるので,本を読んで勉強することがおもしろいのです。
城ヶ崎先生に,違いを話したら,その視点が勉強になると言っていました。
この「視点の違い」というのは,若い頃からよく言われていて,私はどうも見方が普通ではないようです。
たぶん,気に入った角度を見つけてはそこからじっと見てしまうのだと思います。
何事もそうですが,ちょっと角度を変えると,別の姿が見えてきます。
そういう話がスクーの主な話になります。
こんな話からスタートし,最後は,城ヶ崎先生に宿題で終わりました。
城ヶ崎先生は,次回から数回にわたり,私に講義をします。
聞き手が私ですから,大変だと思います。
ですが,これも人生です。
これまで城ヶ崎先生が学んできたことを,ある意味総括するような感じで,語ってもらいます。
--
そのスクーですが,「横山験也の算数の授業」を「受けたい!」という方が,100名を超えました。
ありがたいことです。
今日は,その準備として,久しぶりに世阿弥の本を開きました。
また,日本書紀も開きました。
日本書紀の確認したかったページの近くには,お気に入りの,「宮門を通るときの作法」が載っています。
算数からちょっと離れ,そっちを読み,「なるほど,勉強になるな」とつぶやきました。
--
 城ヶ崎先生の鞄に入っていた本を紹介しましょう。
城ヶ崎先生の鞄に入っていた本を紹介しましょう。
宇佐美寛先生の『私の作文教育』です。
さすが!と思った次第です。
久しぶりに,深澤先生とセミナーでご一緒しました。
私が還暦を迎えたので,深澤先生が何かセミナーをと考えてくれ,それを土作先生が実行してくれました。
土作先生ともご一緒するのは久しぶりで,全体的に懐かしさがありました。
そういう懐かしさの中,マイペースで1時間お話しさせていただきました。
「算数的体験を」という,実に真っ当な話です。
その話をしている間に,グイッと姿勢が良くなった先生がいました。
名前を聞きそびれましたが,とても嬉しかったです。
懇親会で若い先生と話しました。
話をしていて,人生の深みに入っていく先生がたまにいます。
そんな先生が,今回は珍しく2名もいました。
藪田先生と西野先生です。いい感じで成長してほしいです。
また,私の講座中,切れ味のいい先生が1名いました。
小野先生です。
こういう若い先生が,近い将来の教育界で大活躍をしていくのだろうなと思います。
--
 翌日は,木更津での野口塾です。
翌日は,木更津での野口塾です。
その懇親会で,明石要一先生が主催するSG会の情報が入りました。
なんと,7月のSG会の課題図書が宇佐美先生の『私の作文教育』です。
嬉しいですね。
SG会でどんなレポートが出るのか,楽しみです。
でも,開催日が一週間ずれるとの情報も入りました。
その日は,他の予定が入っているので,参加できません。残念!
この頃,ちょっと忙しくて,東京へちょこちょこ出かけています。
1つは,来年度から使う新しい教科書の展示会が開催されているので,ちょっとのぞきに行ってきました。
なぜか,ほぼがら空きです。
ですので,余裕を持って算数の新しい教科書を開きました。
算数はそんなに大きく変わっていないと感じています。
--
スクーの番組をどんな内容にしていくのか,ということの打ち合わせもありました。
若いビジネスマンが主な視聴者ということだったので,テーマの絞り込みなど,ちょっと時間がかかりました。
算数で行こう!ということになり,そこから先はスルスルでした。
タイトルは「横山験也の算数の授業」です。
なかなかいい感じです。
29日(日)午前11時~11時30分は,その第1回目です。
分数がテーマです。
「ちょっとだけ,見てみるか」と思われた先生は,下からサイトに入り,「受けたい!」をクリックしてください。
http://schoo.jp/class/930
サイトにはいると,右の方に「受けたいと言っている学生の声」があります。
その1番下(最初の声の発信者)に中西孝之さんが一言コメントしています。
この人,スクーの社長さんのようです。
--
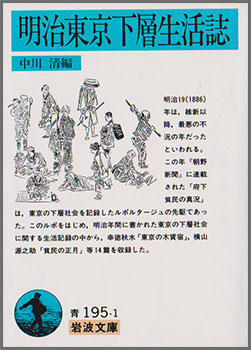 東京への道中は,やっぱり読書です。
東京への道中は,やっぱり読書です。
『明治東京下層生活誌』を読んでいました。
驚きの事実を学べるので,ちょっとはまっています。
また,漢字も勉強になっています。
◆ちゃんと→秩然と
ちゃんとの「ちゃん」を漢字で書いていたことに驚きます。
さらに,その漢字から察する意味にも驚きました。
おもわず,余白にペン書きしました。
さらに,単語登録もしました。
ですので,「ちゃんと」と打つと「秩然(ちゃん)と」と出るようになりました。
今日は新宿へ行くので,漢字に注目しつつ,再度この本を読み返して見たいと思っています。
--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















