野口芳宏先生の講義を何度も授業していると,「公」と「私」という考え方が滲み込んできます。
講義を拝聴していて,繰り返されるのが,次の2つです。
「私」が強くなると,我が儘になります。
「公」が強くなると,しっかりした人になります。
当たり前のことですが,言われ続けて,なるほどと滲みてきます。
そこで,この野口先生の教えを算数的な図で表してみました。
それが,「公私の分数」です。 
分子の「私」が小さく,
分母の「公」が大きい。
この状態を,算数では「真分数」と言います。
「真(まこと)」の分数です。
逆に,分子が大きく,分母が小さい状態を,日常では「わがまま」と言います。
算数的には「仮分数」です。
「仮分数」という見方をすると,自然に「仮(かり)」の姿なんだという思いを与えてくれます。
わがままな子は,恒常的にわがままなのではなく,たまたま「私」が大きくなっているのが続いているのだと見なせます。こう思うと,何かしらの施しようがでてきます。
「公」を大きくするのに有効なのは,子ども達を惹きつける授業をすることです。
「先生,私にもやらせて」と思わせる授業をすることです。
なぜでしょう。
それは,「私もやらせて」と思ったとき,自動的に「公」が子どもの心に広がるからです。
ちゃんとしてないと,先生が自分を指してくれないことを知っているので,「公」を自ら大きくしてくるのです。
「公」の自覚させる良いチャンスになっています。
算数ソフトを使うと,「私にやらせて状態」はすぐに巻き起こります。
ですので,ちょっとした行儀作法の指導を入れると,真分数の子を育てる方向へも道が伸びていきます。
藤本浩行先生の御尽力で,山口県の徳山市でお話しをしてきました。
「作法」と「算数ソフト」です。
浅村先生,村井先生ともお会いでき,とても楽しい一日になりました。
懇親会は驚きまくりました。
「算数ソフトの実践交流会」という状態でした。
延々とこういう事とがあった!と話しが続きます。しかも,その話しがどれもこれも驚きの連続です。
とくに,際だって驚いたのは,佐藤先生が平均点20点台の女子,平均点60点台の男子をともども90点に引き上げたことです。女子は450%アップです。考えられない向上です。それと同時に,どうして平均点20点なんて事になるのか,そっちの方が気になりました。聞けば,完璧なまでの無気力だそうです。それが,ソフトを持ち出したら,反っくり返っていた体が前向きになり,無言の子が声を上げ・・・。あっと言う間に1単元が終了しテストをしたら,男女共々平均90点越えです。5年生でも,ソフトを使うと急速に生き返り,意欲的になるのです。
藤本先生からも次々とソフト実践のドラマを伺いました。
そうして,「算数ソフト実践」を交流する会を東京で開こう!と,なりました。
代々木にオリンピック村があるので,そこで・・・と声が上がったら,阿蘇青少年の家に勤務されている片野先生が,それは勤務先と強い関係のあるところで・・・と,これもまた盛り上がりました。
佐藤先生は,関東で算数ソフトのお話しをしてくれそうな先生方のお名前を次々とあげていました。若いですが,交友関係が実に広いです。それだけでも,素晴らしいことです。
藤本先生や佐藤先生が切り盛りして,良い会が開けて,その上,色々な視点で実線や活用法を紹介できたら,それを本にする道も見えてきます。
今回の徳山の会は,算数ソフトがいよいよ使う先生方のお力で前進していく大きなターニングポイントになったような気持ちになっています。
私も側面から,しっかりと応援をしていきたいと思います。
「作法」の方でも,ちょっと驚くことがありました。
家に帰ったら,熊本の桑崎先生からフェイスブックメールがありました。熊本市にある山崎菅原神社の宮司さんが発行している「ひとひらのことのは」というニュースレターの最新号に私の作法の本が紹介されていると,知らせがあったのです。
PDFが添付されていたので,早速読みました。 写真入りで『明治人の作法』が紹介されており,「お子さんがいらっしゃる方だけではなく,多くの方に読んでいただきたい一冊です」と結ばれていました。
作法の話しをしてきたばかりだったので,感慨深く読ませていただきました。
作法も,ディレクターで作ったソフトを使ってお話しをしました。
若い先生が,「あのソフトが欲しいのですが・・・」と申し込まれました。算数ソフトは有料ですが,作法のソフトは無料でおわけしているので,メールアドレスを送って下さいとお話ししました。
そうして,帰り道,倉敷で途中下車し,新納先生とお会いしました。
懐かしい話しもしましたが,新納先生の研究を伺ったら,急に盛り上がりました。
やっぱり,真剣に取り組んでいる話しは面白いです。
新納先生は研究を進めるうちに,自分の人生観そのものまでが代わりつつあるというのです。これは,素晴らしい研究です。単なる頭の研究でなく,生活に還元できる研究です。ある意味,私の作法の研究に似ています。
きっと,新納先生の研究は,時間と共に,世の中から求められるようになり,新納先生のお考えを取り入れています」という声も思わぬ所から上がるようになると思います。
私も新納先生から学びつつ,しっかりと応援していきたいと思います。
珍しく,教育系の本から原稿依頼が来ました。
自分が書ける内容ではないので,見送らせていただきました。
今回の依頼も電子メールでした。
若い頃は,封筒で届いていたものです。そうして,その封筒には「原稿御依頼」のスタンプが押してあます。そのスタンプを見ると,フッといい気分になっていました。
封筒の中には「諾否ハガキ」というのが入っており,諾か否かに丸をつけて返信します。
すぐに返事をした方が,編集の方にとって良いだろうと思っていたので,即座に「諾」に丸をつけて投函していました。
この丸を付ける「諾」ですが,どうも,「諾」に丸をしてはいけないのではないかと思うようになっています。
中国の古典『礼記』に次のように載っています。
父命じて呼べば 唯して諾せず
父親に呼ばれたら「唯」と返事して,「諾」と返事はしない
と言うことです。
この「唯」は,すぐに返事をすることです。
「諾」は,驚く無かれ「ゆるゆる返事する」と言うことなのです。
お父様に呼ばれたら,すぐに返事をしましょう。ノンビリとした返事をするのはいけませんよ,という意味です。
こういう事を知ると,「諾」には丸が付けられなくなります。
「諾」を消して,「唯」に直して返信するのが礼となるからです。
つまり,「諾」というのは,依頼者が「ゆっくり考えて良いお返事を下さいね」という気持ちを込めた言葉なのです。それを真に受けて,はいゆっくり返事しましたと応えたことになるのが「諾」なのです。
と,ここまで分かっても,もう諾否ハガキが届くことも無さそうですし,江部さんや樋口さんのような博識の方でないと,「唯」と直してもその意味が通じないでしょう。
漢字の文化がここでも一つ消えていっているように思えています。
--
この「父命呼 唯而不諾」のすぐ後には,閾(しきい)を踏まないという事が書かれています。
これも面白いところです。
私の研究ジャンルの一つに作法があります。作法には算数ソフトのような派手さはありません。ですが,知らないと日本人としてかなりイマイチと感じられるちょっと変わった世界になっています。
ちょっと変わっているとはいっても,それが歴史を持っているので,ぞんざいには扱えません。
なにしろ,万葉集にも作法のあれこれが出てきています。
----
山神(やまつみ)の奉(まつ)る御調(みつき)と
春べは花かざし持ち
秋立てば黄葉(もみじ)かざせり
----
山の神様を奉るといえば,春は花,秋は紅葉だね
というような意味です。
春の田植えの頃に山の神が降りてきて,秋の収穫を終えて山に帰ります。大事な「始まりと終わり」ですから,それなりの儀式を行います。
その時に,春に葉を奉り,秋に花を奉ったんじゃ,それってダメじゃん!と万葉の時代にはなっていたのです。
この感覚を伝統的に受け継いできているから,日本人はやっぱりすごいと思います。
事の始めとと終わりにはそれなりに何かしましょうというのは,今も昔も変わりませんが,何をするかは時代と共に変わってきています。
特に,日常生活の作法は明治になって変わりました。全国,不統一だった作法を当時の文部省が「こうしましょう」とガイドラインを示したのです。この水準が高かったので,戦後,フランクな時代になっても日本人は礼儀正しい人柄として世界に認められています。
この『行儀作法の教科書』がお陰様で増刷になりました。3刷りです。たくさんの方々に読んでいただけて,とても感謝しています。
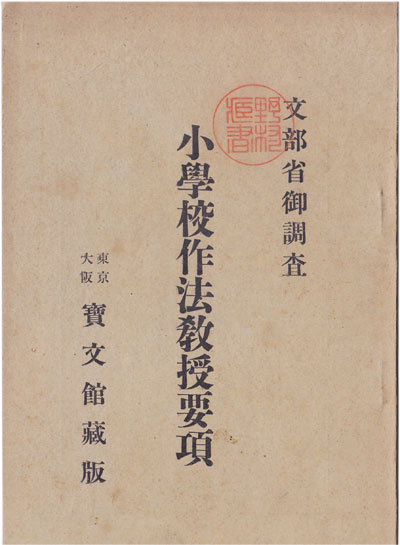
学校が指導する行儀作法の原点となる本がこの本です。
作法教授要項は大正時代に入ってから正式に発表されたのですが,その前の明治44年に,この本が全国の師範学校や教育委員会に配布されました。
何のために配ったのかというと,小学校で実際に指導に当たっている先生方からのご意見を伺うためです。
そうして,意見を集約し,大正2年に正式に「小学校作法教授要項」は発表となりました。
このあたりの経緯が,序言などに記されている大変珍しい本です。
この半年後に中学校の作法教授要項の本も配布されました。
この本,表紙に蔵書印がありますが,保存状態がとっても良いです。よくぞ,こんなに良い形で残っていたものだと感心させられています。
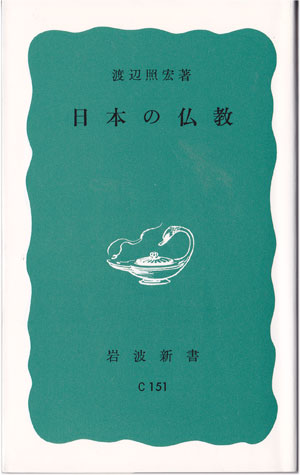 意外なのですが,この『日本の仏教』は学級経営の根本的なところに役立つことが書かれています。
意外なのですが,この『日本の仏教』は学級経営の根本的なところに役立つことが書かれています。
「形を重視する」ことの大切さです。
とまあ,このような結論めいた内容を示されても,そんなことでは人の頭は納得しません。
学級経営には「形」といわれるものが存在しています。
例えば,「起立」と言われれば,立ち上がり気をつけの姿勢をします。
これも一つの形です。
このような形を取らないと集団の挨拶ができないのかというと,そんなことはありません。
座ったままの会釈でも,挨拶をしたことになります。
なぜ起立をしたくなるのでしょう。
なぜ起立をさせたくなるのでしょう。
こういう具体的なことが書いてあるわけではありません。
たとえば,起立のようなことがなぜ生じるのか,そこに日本人の気質がでて来ているのです。
そのことが仏教というフィルターを通して,実に良く示してくれているのがこの本です。
直接的に役立つ事ではなく,腹にズシリと来る,そういう本です。
武道や茶道など「道」と名の付く修行を体験されたことのある先生は,良い感じで腑に落ちると思います。


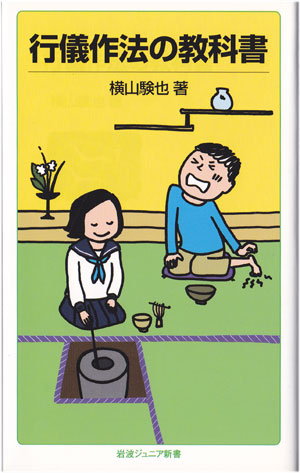
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















