1,分配法則
(a+b)×c=a×c+b×c
※aとbを分けて配ります。
2,交換法則
a+b=b+a
※場所を交換しています。
3,結合法則
(a+b)+c=a+(b+c)
※結びつきを変更できます。
このなかの「分配法則」が,子ども達にはちょっとわかりにくいところです。
それを先日1本ソフトとして作りました。
そのソフトを使って,早々に授業をされた佐藤先生から「多いに盛り上がった!」と喜びのメールをいただきました。
授業用として,充分に役立つことが分かり,とても嬉しい気分です。
しかしながら,もっとよく理解しやすくするには,もう少し演出が必要と,友達の藤本浩行先生(『新任教師 始めの一歩』の著者の先生です)からアドバイスを頂きました。(コラボソフトの始まりです!)
しばし,考え,左右を見比べるタイプも作ってみました。
右の図を見ても,見えてこない特色を記しましょう。
吹き出しの先生がボタンになっています。
先生ボタンをクリックすると,「=56」がジワーッと消えていきます。
次に,「(5+3)×7」と「5×7+3×7」がジワジワと近づきます。
そうして,最後に,図の間にある「=」が下にスーッと降りてきます。
こうして,分配法則の形ができます。
そこに出てきた「きまり」ボタンをクリックすると,●や■や▲を用いた分配法則の式が出てきます。
有り難いのは,「クリック」や「桜スライダー」で数値を変更できることです。
「理解」そのものをしっかり頭に染み込ませることができます。
「桃太郎」ボタンをクリックすると,トックンができます。
理解したことを,繰り返し,今度は体に染み込ませます。
※1つ前のソフトも,このソフトも,今すでにアップされています。
このソフト,もうほんの少し作り直したいと思っています。明日か明後日には,差し替えます。
ご覧のように,「底面積×高さ」へと誘う作りになっています。
吹き出しの中に,メクリがあります。
この下,気になりますよね。
先日,チーム算数で「墨塗り教科書」をみんなで眺めたのですが,みなさん「墨の下」が気になっていました。
隠されていると,気になってしまいますよね。これが,集中を生み,また,頭が考えようとします。
1,集中を生む
2,考えようとする
子ども達が,こういう有り難い状態になってくれます。
ここで,国語の複合語が得意な先生は,吹き出しの中の文字に着目して,
「底面」+「面積」
ここからどう短縮語を作るか,考えさせても面白いです。
「面」がダブっているから・・・・
とピンと来る子が多いと思います。国語のセンスも良い感じと言うことになります。
「もっと!算数」サイトにアップされましたので,お時間のある先生,ぜひご覧下さい。
--
友達の藤本浩行先生の『新任教師 はじめの一歩』が教育書のフェアで展示されると聞いています。
嬉しいですね。
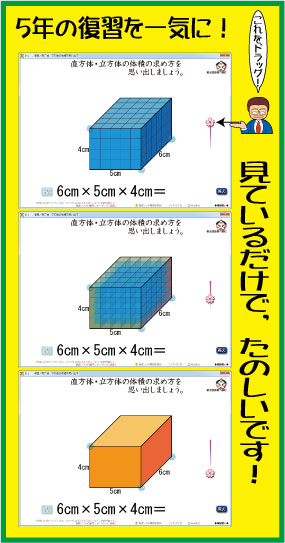 6年生の体積。その導入で使うソフトができました。
6年生の体積。その導入で使うソフトができました。
導入ですから,まずは,復習をします。5年生で習った,「直方体・立方体の体積」の復習です。
工夫した点は,ソフトを立ち上げると,基本中の基本のブロックタイプの立体が登場します。
これを見て,体積は縦・横・高さに並べて積んだ数を調べることが一気に思い出されます。
その後,桜スライダーを下に下げると,ブロックが消えてゆき,変わりに「縦横高さ」のフレームが出てきます。
これで,ああ,そうだったとなります。
ソフトを見せて,ものの数分で一気にここまで来てしまいます。
面白いのは,立体の頂点がドラッグできることです。頂点にある丸いボタンをドラッグすると,横幅3cmになったり,奥行きが1cmになったりと,思った寸法に簡単に変更できます。
これで,3問ほど体積を実際に求めてみるのもいいですね。
公式も思い出して欲しいところです。
右上にある「桃太郎」ボタンをクリックすると,桃太郎道場画面に切り替わり,公式を復習できるようになっています。
6年生の先生,使えるようでしたら,ぜひ御活用ください。
このソフトは,今日,「もっと!算数」サイトにアップされました!
うれしいです!
この先,三角柱のソフトと,角柱の公式を考えるソフトの2本を作る予定です。
今しばらく,お待ち下さい!
 5年生の「小数を分数に直す」ソフト。
5年生の「小数を分数に直す」ソフト。
これを奥田先生がパソコンで動かし,ビデオに撮影してくれました。
わずか4秒ですが,小数が分数になる様子がよく分かります。
それを,ユーチューブにアップしてくれました。
大事なポイントは,一の位に単位となる「1」が来ると言うことです。
それ以下の所には,何もない「0」が続きます。
それが突然現れて,下に降りていき,分数となります。
赤でかいてある「10」が,ソフトを使わなくても見えてくれば,OKです。
このソフトですが,レベル1,レベル2,レベル3,レベル4と4段階で学習できます。右の小数第1位までのは,レベル1です。
レベル4は,下のように何十~小数第2位の数になっています。
十の位が登場することで,一の位に1を立てる意味が深まります。
最後には,帯分数にする機能もついています。
どんな表現になっているのでしょうか。子ども達に「算数の表現」を考えさせるのも楽しい一時になりますね。
もっと算数にアップしていますので,関心のある先生はぜひご覧下さい。
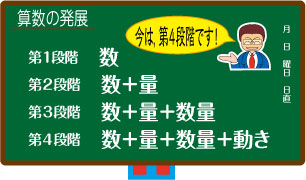 昔の算数の教科書を見たことがありますか。
昔の算数の教科書を見たことがありますか。
アッと驚くほど,数・数・数・・・のオンパレードなのです。
今の時代の教科書を知っている先生方には,すぐさま「これじゃあ,分からない子がたくさん出るだろうな」と感じると思います。
「わかりやすさ」という視点で,ザラッと算数の教科書を昔から見ていくと,なんとはなく4つの段階になっているように見えてきます。
第1段階は,「数」の時代です。
数や計算一色という感じの時代です。
それが,次第に挿絵が増えてきます。太平洋戦争中の1年生の教科書は,ほぼ全部絵で,逆になんだか??という気にもなるぐらいです。これが第2段階です。
第3段階は,数直線・線分図の登場です。戦前から数直線は教育書などには出てきていますが,教科書はちょっとひ弱でした。それが,戦後,随所に出てくるようになっています。
数直線は,「数」と「量」を同時に示している「数量」の表現です。デカルトの発明で,非常に優れた表現です。
そうして,最近,教科書の巻末に手作り教具がおまけとしてついて来ています。
この手作り教具は,「数」「量」「数量」とは全く異質の表現を含んでいます。それが「動き」です。
教科書には取り入れられていませんが,「動き」を実に巧みに実現させているものがあります。
皆さんが使ってくださっている「算数ソフト」です。これが,第4段階です。
算数の勉強をしている先生は,「数」「量」「数量」については目にしているので,それほどの違和感がないと思いますが,「動き」は算数としてあまり聴かないので,「どうなの?」と感じると思います。
「動きは算数じゃないよ!」そう思う先生もいると思います。
でも,「動き」は,算数の本質的な部分なのです。
「数」「量」「数量」は,算数の「結果」を示した表現です。
それに対して,「動き」は算数の「過程」を示しているのです。
このように一言で言われても,わかりにくいだろうと思いますが,その「過程」は「連続」という姿を持って表れ,どうも5種類あると私は見ています。
この「動き」の表現,特に算数ソフトによる動きの表現は,子ども達の理解・定着を著しく上昇させています。
第1段階から第2段階へ発展したときより,
第2段階から第3段階へ発展したときより,
はるかに大きなわかりやすさを子ども達に与えています。
新しい衝撃的な研究領域。それが算数の「動き」です。
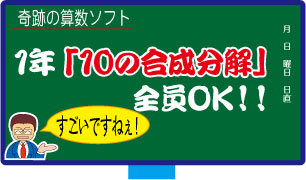 「10は2と?」
「10は2と?」
こんなの簡単!と思われるところですが,なかなかサッと答えられない子がいます。
数を「数える」ことに慣れ親しんでいるので,2つに分けたり,組み合わせたりすることには,とまどいを感じるのです。
それなので,おはじきやブロックなどを使って, 「10は4となんだ」など,具体物を見ながら勉強をくり返します。
それでも,イマイチの子がでてきます。
数えられるならそれでいいよねと,軽めに扱って次へ進んしまうことも起こりえます。でも,これはなりません。10の合成分解の考え方が,繰り上がりのあるたし算の途中に,中継する思考としてしっかり位置付いているからです。
ですので,この勉強は教科書の該当ページが終了しても,折を見て繰り返ししっかりと定着させていくようにします。
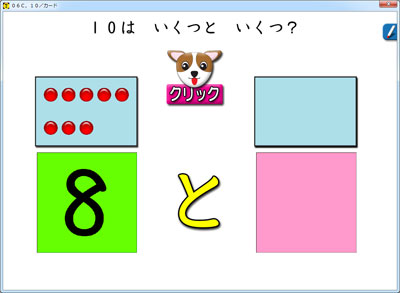 1年生の教室に算数ソフトをもって授業に入った山本先生。
1年生の教室に算数ソフトをもって授業に入った山本先生。
そうです。あの『伝わる伝わる見える指導』の山本正実先生です。
奇跡の算数ソフトをPCにセットして映し出し,リズム良く,繰り返し30問ほどやったそうです。(5分もかかっていません)
1年生なのですが,すでに勉強時間に「ウップー」とうつぶせ気味になる子もいます。
そんな子も,みんなどんどん答えて,最後には全員の子がすっかり分かるようになったそうです。
ご覧の画面のように,犬をクリックすると,「8」が他の数に早変わりします。
答えは,水色とピンクの四角をクリックすれば,直ぐに見る事ができます。
効果音も適度に鳴って,雰囲気を盛り上げてくれます。
くどくど説明するより,どうなるかを繰り返し見る事が大切です。繰り返し見る内に,そこに横たわるきまりに子供自身が気付くからです。
自分できまりに気付くから,とっても面白く感じるのであり,また,忘れにくいのです。
『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』1年1巻です!
算数ソフトを使わずに授業を進める事は,見方を変えると,わかりにくい授業をしている事になります。
奇跡の算数ソフトをじゃんじゃん使いましょう!子ども達の学力増進のために!

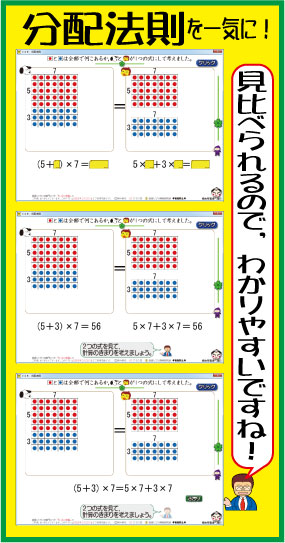
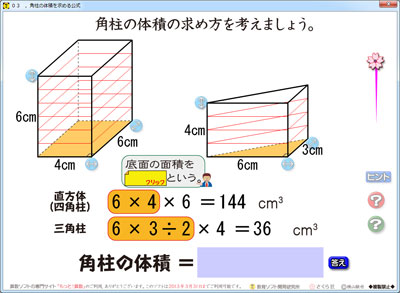
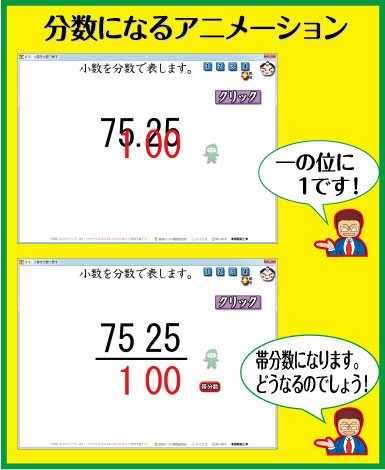
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















