
愛媛の松澤正仁校長先生から,左の『第19回 名人に学ぶ教育講座 全記録』をいただきました。
表紙に目次が見えますが,4つの講座があり,私は1の「算数 6年『速さ』」と,3の「作法講座」を担当しました。
当日の講座すべてを,宇和島教育サークルの方々がテープ起こしをされ,編集してくださったものです。
とても,読みやすいです。
「作法講座」では,「姿勢」の話をしました。
1コマ全部姿勢の話ですから,聞いていた先生方も少々大変だったと思います。
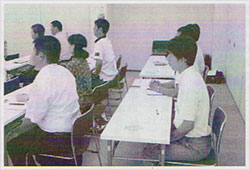 何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。
何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。
背休め(背もたれ)に,背中が触れません。
体は多少きつくなりますが,やってやれないことではありません。
良い姿勢は,ただそれだけで良いですよね。
皆さん,凜としています!
姿勢正しい,凜とした日本人。
これですね。
手元に,明治34年に刊行された『小学作法書』(茨城県師範学校長 鈴木亀寿閲 湯澤直蔵著)があります。
 この作法書の第四は,「教室内における心得」です。
この作法書の第四は,「教室内における心得」です。
その一番目は,姿勢です。
姿勢を教室内の作法として,第一に取り上げています。
一,教室内にありては,姿勢正しく着席すべし。
補足として,次のように書かれています。
姿勢正しからざれば,自然に風采挙がらず,また体格を損じ,身体の発達を妨ぐるに至るものなり
よくよく注意すべし。
良い姿勢をすると,それだけで,10の功徳があることを,九州大学医学部の教授だった池見酉次郎先生が『人間回復の医学』(創元社)に記しています。
明治期の先生方も,姿勢が体に影響することを知っていたのです。
池見先生の話も,作法の講座で話しました。
その記録が,とても読みやすく編集されています。
関心のある方は,松澤校長先生へご連絡下さい。
算数ソフトを購入したい!
カタログが欲しい! 急ぎで!
そんなときに便利なサイトがありました。
教科書供給協会のカタログスタンドがあります。
そこに,算数ソフトのカタログがアップされています。
プリントアウトして,是非,ご活用下さい。
--
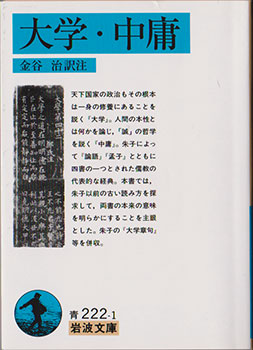 『大学・中庸』(岩波文庫)を読み返していたら,事前学習法にちょっと関連する言葉が載っていました。
『大学・中庸』(岩波文庫)を読み返していたら,事前学習法にちょっと関連する言葉が載っていました。
ご紹介します。
物に本末あり,事に終始あり,先後する所をしれば則ち道に近し。
岩波文庫の訳には,下の通り記されています。
ものごとには根本と末端とがあり,
また初めと終わりとがある。
〔そのことをわきまえて〕
何を先にして何を後にすべきかということがわかるなら,
それでほぼ正しい道を得たことになるのである。
事前に何をするか。
事中に何をするか。
事後に何をするか。
こういう意識もって実行することが,古来よりの「正しい道」なのです。
事前学習法は,その事前を特に意図的に行おうとする授業方法です。
この秋に,事前学習法セミナーが大阪と東京で開催予定です。
11月15日(土)第1回 事前学習法セミナーin大阪
12月14日(日)第2回 事前学習法セミナーin東京
若い先生方が語ってくれます。
今から,楽しみでなりません。
千葉の佐々木先生も,事前学習法に興味を示してくれています。
ありがたいことです。
いつものジョナサンで会って,話をすることになりそうです。

宇佐美寛先生の『私の作文教育』に,次のように記されています。
「作文の思考には,このように知覚的側面がある。しかし,この問題については,私はまだ不勉強で明確には書けない。代わりに,次の本を読んでいただきたい。」
と,この後に2冊紹介されています。
「①池田久美子『視写の教育--<からだ>に読み書きさせる』(東信堂,二〇一一年)
②石川九楊『縦に書け!』(祥伝社新書,二〇一三年)」
『縦に書け』は,『視写の教育』同様,実にいい内容です。
この本を読む前の私は,縦に書こうが,横に書こうが,鉛筆で書こうが,キーボードを打とうが,「どれも大差なし!」と思っていました。
縦書きの持っている世界観を知らなかったからです。
無知は,恐ろしいです。
成長できるチャンスを自分でつぶし続けるのです。
この本を読で,私は「縦書きだな」と思い改める気持ちになりました。
幸い,作法関係は縦書きでノートに書いているので,これを一層しっかり進めたくなっています。
この縦書き指向になったのは,「姿勢」「立腰」を楽しんでいる自分に,確かな変化が起きているからです。
普通,座っているときの姿勢なんか,「どうでもいいじゃん!」と思います。
それなりに,見苦しくなく座っていれば,背もたれにもたれていても,それが楽なら,「いいじゃん!」となります。
これも,姿勢の持っている世界観を知らないところから出てくる言葉です。
皆さんの中に,ただ座っているだけでほめられたことがある人,いますか。
そういう人は,極めて少ないでしょう。
「良い姿勢」「正しい姿勢」をほめられることで,外から「良い」とか「正しい」,そういう人としてほめられます。人の評価が,自分を形成してくれます。
外からだけでなく,姿勢を良くしていると,正しい方向に自然と向かう自分が出てきます。
なぜ,正しい観念が生じてくるのか。
それは,姿勢という言葉と体が連動するからです。
良い姿勢をしていると,そのこと自体で「良い」という世界観に自分が包まれます。
正しい姿勢をしていると,そのこと自体で「正しい」という世界観に自分が包まれます。
姿勢を良くすることは,その姿を言い表す言葉によって,自分をじわじわと変えていきます。
姿勢の世界を知っているからこそ,出来る自己変化です。
『縦に書け!』に,次のように書かれています。
「字や文を書くとき,紙は単なるのっぺりとした空間ではなく,天と地を持つ現実の世界を象徴する表現空間になります。」
これを知った私は,姿勢同様の大きな何かを得られそうです。
縦書きを意図的に行い,この世界からも成長をしていきたいと思います。
宇佐美先生の本に引用されている本には,外れがありません。

教育の原点セミナー。
野口先生のお話は,今回も圧巻でした。
暗記することより,書いてある文字をしっかり見ながら読むことが大切なのです。
「読経」
この文字から,その意義が伝わってきます。
--
早川先生からは,野口先生,青木幹勇先生,芦田惠之助先生の全集・著作集からのお話です。実際に書かれていることから語ってくれました。ハッとすることの連続でした。
習字の実技も兼ねた平井美穂先生の話も,濃かったです。5ステップは,「スイートポテト」に通じる世界があり,とても納得しました。
山中先生の素材研究に初めてマトリックスが登場。これを使うと,書き込みたくなるので,とてもグッドです。
そうして,圧巻は,神部先生と五十嵐先生の音読指導の現場。
教わる役の五十嵐先生が,途中でくじけてしまうのではないかと思うほどの指導でした。でも,五十嵐先生は途中からボイスレコーダーを取り出し,それを机の上にキチッと置き,気合いを入れて受けていました。その後は・・・,すばらしい音読になり,非常に感動しました。
参加された皆さんから,一言感想をいただきました。
そうしたら,大野聡美先生から,私の姿勢がとても良かったとほめられました。
私に姿勢の大切さを教えてくれたのは,野口芳宏先生です。
 『道徳授業の教科書』にも,次のように記されています。
『道徳授業の教科書』にも,次のように記されています。
-------
まずは,聞く「姿勢」「態勢」づくりが肝要である。森信三先生は「立腰」ということを説かれ,「この一事を子どもに躾けられたら,親として我が子への最善最大の贈り物である」とまで述べておられる。私もこれにいたく心を動かされ,気が付くたびに「立腰」に戻るように努めている。(p41)
-------
私も野口先生から,「最善最大の贈り物」をいただいた気持ちになっています。
姿勢を正しくすることは,ただそれだけで,自分の心を正しい道へ導いてくれます。
出来るだけ姿勢を正して。
気がついたら姿勢を正して。
姿勢を楽しむ先生が増えれば,姿勢を好む子が増えます。
日本の大切な精神の一つが復活します。
--
原点セミナーに,若い先生が参加していました。
その中に,山﨑敏哉先生と藪田顕嗣先生がいました。
この両先生も,すこぶる姿勢がいいです。
3人寄ると,話は事前学習法になります。
2学期が始まって,まだ,間もないのですが,その成果がしっかり出ているので,
「事前学習法のセミナーを東京で開催しよう!」ということになりました。
講師は,山﨑先生と藪田先生!
予定日は,12月14日(日)です。
「第2回 事前学習法セミナーin東京」です。
なぜ,第2回かというと,第1回は「事前学習法セミナーin大阪」が11月15日に開催されるからです。
懇親会で小出先生と藪田先生と私の3人で事前学習法で盛り上がりました。
小出先生は1年生で実践中です。これで,講師は3名となりました。
楽しみです。
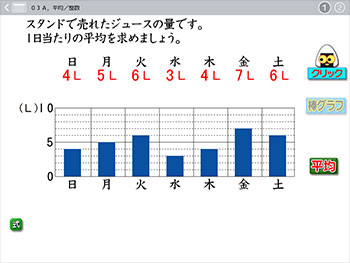 「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。
「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。
----------
丸岡会長曰く
35分で指導書2時間分を進むことが出来ました。
----------
5年生の「平均」の単元を,倍速で授業が進んでいます。
これは,まさに驚異的です。
驚くことは,まだあります。
学力の劣る子が集まるグループでも,他のグループと同様に,説明していたとのことです。
事前学習で学力格差をググッと縮めたので,それが「言語化する活動」にも大きく影響を与えました。
発表した子は,自信を持ったでしょうね。
もし,普通に授業をしていたら,この子達は控えめに時間を過ごしたことでしょうね。
説明は,おぼつかなかったと思います。
でも,運良く,丸岡会長が事前に平均のソフトを見せてくれたので,ガラッと変わったのです。
自分で教科書問題を考え,説明できるようになったのです。
この子達,もしかしたら,事前学習を受けることで,めきめき力がつくかもしれません。
そうなってほしいです。
--
明日は,東京未来大学で「第5回 教育の原点セミナー」です。
このセミナーに,事前学習法研究会の藪田先生と山﨑先生も参加されます。
事前学習法+算数ソフト=驚異の成果
この図式について,藪田先生の実感を聴いてみたいと思っています。
昨日の夜,「事前学習法」の第1報が,丸岡会長から届きました。
続けてすぐに,第2報が藪田先生から届きました。
さらに,第3報が山﨑先生から届きました。
今日は,第3報の山﨑先生の「事前学習法」のご紹介しましょう。
6年生の「拡大図と縮図」の第1時です。
------------
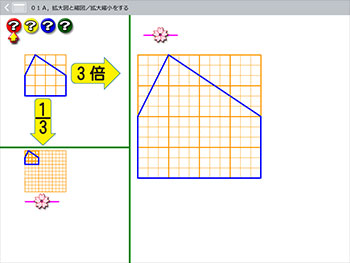 山﨑先生曰く
山﨑先生曰く
本時のめあては「拡大図と縮図の意味を理解する」ことでした。
はじめ10分間、算数ソフトの1つ目を見せました。
拡大・縮小を子供と会話をし笑いを交えながら実際にやってみせました。
ほとんどの子供はすぐにそれぞれの仕組みが分かったようでした。
教科書だけですと動きはもちろんありませんから、拡大・縮小の意味をつかむのは感覚として難しいと思います。
算数ソフトで事前学習の導入をしたおかげで、授業のはじめの10分ですべての児童が本時のめあてを達成できている状態になり、同じ土俵にのってから授業をスタートすることができました。
めあてに対する格差をなくすことができたので、残りの35分間でゆっくりと比の関係や、他の形での拡大・縮小について学習することができました。
はじめに格差をなくし、授業や単元の見通しがもてているので、2時間通して達成するめあてを1時間で終わらせることができました。
-------------
本時の前に,どのソフトを見せたらいいか決めています。
この教材研究がいいですね。
選んだのは,たったの1本。
その1本を10分ほど,子ども達と見ることで,全員が本時のめあてに到達したのです。
こうなると,授業には余裕が生まれますね。
子ども達は,拡大図・縮図が比と関係があることもつかんだのです。
第1時です。十分な学力を得たといえます。
注目すべきは,最初の10分で,「めあてに対する格差をなくすことができた」ことです。
本時のめあてに必要な学力を,事前学習で授けたのです。
これ,スポーツで言えば,「基礎ルールをみんなが理解した状態」です。
話し合いがみんなで出来ますよね。
実際に,山﨑先生の授業では,格差がなくなったので,授業に推進力がついたのです。
2時間かかるところを,わずか1時間で終わりました。
ガリ勉風な授業でなく,余裕のある授業でこの成果です。
山﨑先生の授業から,
1,1本のソフトで事前学習ができる
2,「めあての格差」をなくせば,授業はスイスイ進む
そういうことが,伝わってきました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)














