昨日の朝日新聞の朝刊「花まる先生」に,関大初等部の三宅貴久子先生が載っていました。
『 関大初等部式 思考力育成法』に記されている,思考スキルの一つ「ピラミッドチャート」の使い方指導の場面でした。
もうすでに,本をお読みの先生には,「あっ!あれね」 とすぐにおわかりと思います。
三角形の中を3層にわけた図を使って,考えを3つの異なるレベルに分類して書いていきます。こういう作業を通してかなりの思考力が鍛えられるというわけです。
朝日新聞の記事を読みましたが,もっと詳しく知りたいと思ったのは私だけではないと思います。
紙幅に限りがあるので,他のチャートがあることや,チャートは目的によって選ぶことなど,示されていませんでしたが,それについては本が出ているので,そちらで補うのが一番と思います。
この『関大初等部式 思考力育成法』ですが,お受験の学舎でも保護者の方々に紹介されています。大阪・関西方面でかなり広まっているようです。意識の高い方に,お勧めの一冊です!
宮内主斗先生の新刊,『授業づくりの教科書 理科実験の教科書』シリーズ(3年~6年)です。
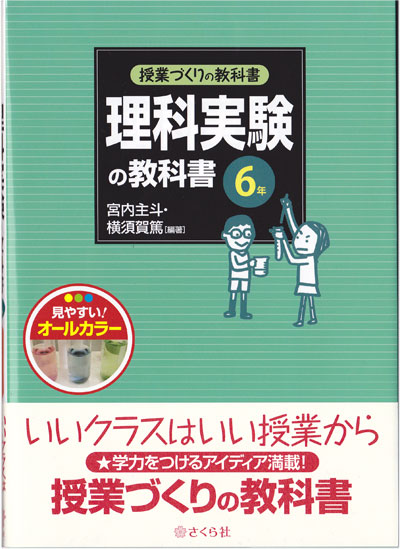
読むと分かりますが,個々の内容が実に濃いです。
実験や観察などこうやると一層良くなることがびっちり示されています。
それに加えて,「やってはいけない」ことも,ページをめくる度に示されています。
単元に入る前に,該当箇所を読んでおきたいシリーズです。
内容の濃さをアップしているのが,全ページ「オールカラー」です。
写真がカラーなので,とてもリアルに伝わってきます。
リトマス試験紙の色もよく分かります!
宮内先生と言えば,理科授業の最先端を歩まれている実績のある先生です。
その宮内先生が,理科好きの先生方とともに作り上げたのが,この本です。
教室に置いておきたい本ですね。
『授業づくりの教科書 理科実験の教科書3年』
『授業づくりの教科書 理科実験の教科書4年』
『授業づくりの教科書 理科実験の教科書5年』
『授業づくりの教科書 理科実験の教科書6年』
友達の山中伸之先生の新刊『できる教師の叱り方・ほめ方の極意』(学陽書房)です。
山中先生は,毎年毎年,本を出しています。
もう,かなりの売れっ子先生です。
山中先生の本を読むと,「こう考えるのか」といった考え方がとても勉強になります。
例えば,序章に何のために叱るのかが書いてあります。普通は,子ども達を良い方向に育てるためと考えつくことですが,山中先生は違います。教育の目的から考えるようにすすめています。
ハッとさせられます。
叱ることは,政治家の大物もします。お医者さんもしかります。
不良グループのリーダーだってしかります。泥棒の親分もしかります。
誰でも叱るのですが,しかる場合が職業によって違います。
それぞれの職業には,それにふさわしい目的があり,その目的に照らし合わせて,叱る場面がでてきます。
教師の叱りの大元をどこに据え置くのか。
これを山中先生は,教育の目的に置いて話を進めています。
なるほど!と感心した次第です。
叱り方のタブー
叱る心得
叱り方8変化
叱るのが苦手な教師は
ほめ方のタブー
ほめる心得
ほめ方7変化
ほめるのが苦手な教師は
読み応えのある本です。
山田洋一先生の新刊『発問・説明・指示を超える 説明のルール』は,とっても良いです!
読んでいて,何度も「なるほど!」と思った本です。
説明は端的に短く。
そういわれると,そんな気がします。
でも,そうではないのです!
冷蔵庫に入っているケーキを捨てることになりました。短く伝えてみましょう。
「このショートケーキ捨ててくれる」
無駄もなく,やって欲しいことをきちんと伝えています。
これで良いように思えます。
しかし,聞いた人はどう思うでしょう。
えっ?どうして捨てるの?と思いますよね。
これを,「これ2週間も冷蔵庫に入りっぱなしだったの・・・」と,言っていれば,聞いた人も「了解!」となります。過去の経験からの実感がわき起こってくるからです。
説明のポイントは,こういうところにあるのです。
1年生が入学してきました。6年の担任であるあなたは,次のどちらの言い方が好きですか。
---------
A。1年生から「優しいから大好き!」と言われる6年生と,1年生がそばに一人も寄ってこない6年生がいるんです。
B。1年生には優しい言葉遣いで接するようにしましょう。親切にして上げられる子はいい子です。
---------
差は歴然としています。Aはなりたい自分が見えてきます。心に伝わります。
このようにAB2つの言い方を並べて,どのように説明をすると良いのか,それを紹介しているのがこの本です。
その事例数は44!
これだけの事例があると,読み通すだけでかなりの勉強になります。
自分があまりしていない納得のいく説明があることに気付かされます。
そういうところは,声に出して読んでみると,また,なるほどと感じるものが出てきます。
実に良い本です。
推薦します!
友人の横藤雅人先生の新刊『5つの学習習慣』です。
わかりやすく書かれているので,どんどん読み進めることができます。
気に入ったところは,「子ども部屋は「貸す」」という考え方です。これは,作法に通じる実によい考え方です。
子どもの環境を「大満足」にしてはいけません。大満足は,その時はよいのですが,後から「わがまま」とか「甘え」とか,負の心根を持つことになります。
2分3分ほど,満たされない部分がある方が,「辛抱我慢の心」「全体が良いから,細かいところは目をつぶる」といった,良い心根が育つことになります。
特に,子ども部屋は毎日活用するところです。
長い年月をかけて使うところです。
部屋を借りつづける子どもの心に何が育っていくのか,それを考えるだけで,幸せな気持ちになってきます。
「腰を立てて椅子に座らせる」という章もありました。これもいいですね。
「良い姿勢は一生の宝」と横藤先生も記されています。
本当にそう思います。
良い姿勢で座れるようになると,姿勢の良い人がどんどん目に付くようになります。
良い姿勢の人を見ると,それだけで良い気分になってきます。
この本からも,姿勢よく座ることが伝わります。有り難いことです。
若い先生にも,若いお父さん・お母さんにも勧められる良い本です。

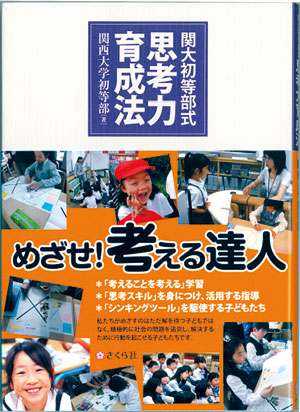
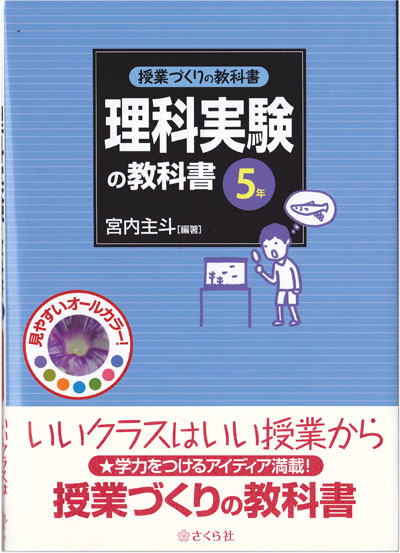
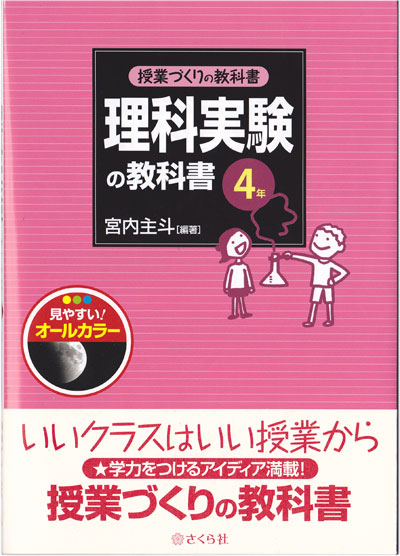
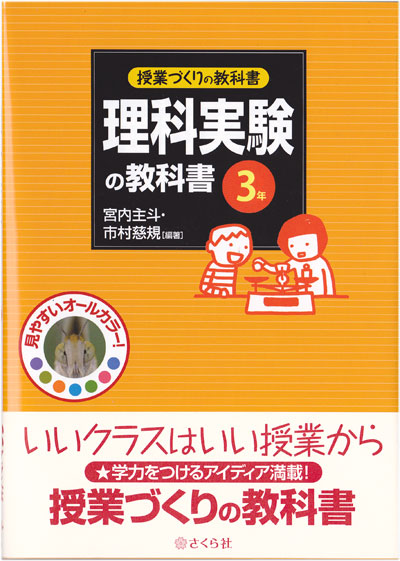
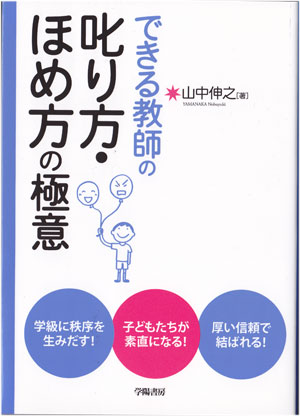
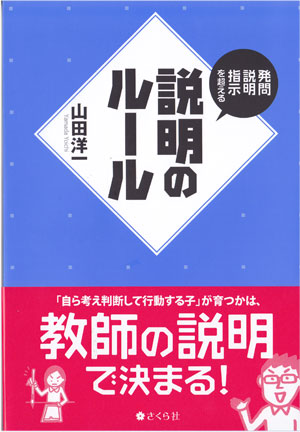
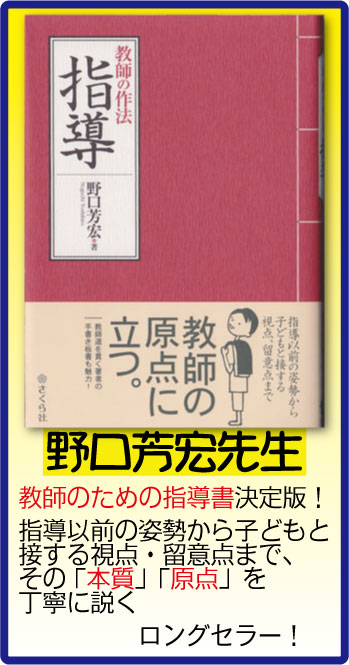
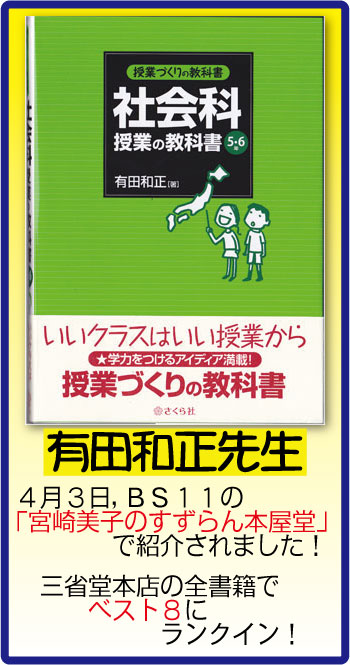
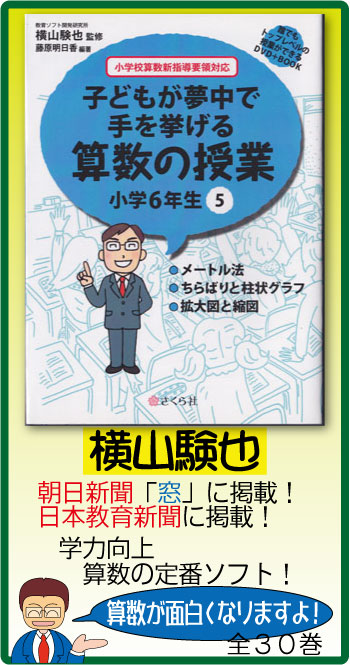
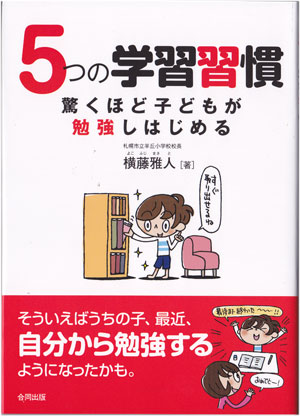
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















