 緒方洪庵と言えば,適塾。ここまでは単なる連携名詞として知っていました。それが,「緒方の塾」という呼び名で,福沢諭吉の『福翁自伝』に出てきて,ちょいとびっくりしました。
緒方洪庵と言えば,適塾。ここまでは単なる連携名詞として知っていました。それが,「緒方の塾」という呼び名で,福沢諭吉の『福翁自伝』に出てきて,ちょいとびっくりしました。
適塾に入門してきた人は何もわからないので,オランダの「ガランマチカ」を入門書として教えます。まず「素読」を授け,「講釈」もして聞かせます。それから,「会読」というテストのようなものを受けさせます。
今風に言えば,「読む」「意味」「自分で解説」ということです。
これができたら,もう一冊同様に行い,その先は各自の研究です。
なんというか,すごいの一言です。私自身の勉強で,いきなりハイレベルなところからスタートしたのは,コンピュータプログラムと,中国思想の時ぐらいです。この両方に通じていていたことは,学ぶ前に「無理かも・・」と思っていたことが,学び終えると強い自信になって,どんどん自分の研究が進んでいることです。
適塾はこれを若者にしていたのです。明治維新になり,大人物が多数輩出したのもわかります。
素読といえば,青森の駒井先生です。『論語』や『大学』を小学生に素読させています。小学生にとっては難解な書を適塾のようにいきなり素読させるのです。それが,その成果は多様で,この夏,2時間もお話をくださいました。
『論語』『大学』を学んだ子が難解な書に自分からチャレンジを始めていく。そんなところの話を,今度会ったときに伺いたいと思っています。
31日:駒井先生からメールが届きました。効能が書かれていました。読書を全くしなかった子が今は『もしも高校生がドラッカー・・・・』『ニーチェの・・・・』など,読んでいるそうです。切れやすい子だったのですが,今は読書で心を落ち着かせているそうです。
--
難書を読めば,本が面白くなり,読書が増える。
難プロを学べば,プログラミングが面白くなり,ソフト開発が増える。
--
要するに,難しいことをやらせれば,そのジャンルが面白くなるのです。
難しいことといっても,全くの素人にとって難しいことです。その道のプロから見れば,明らかに入門的な素材です。でも,それは王道につながるようなまっとうな素材なので,学ぶ人に大きな変化が出てくるのです。
ちょっとずれますが,論語などを繰り返し読むようになると,親孝行になり礼儀もよくなります。礼儀作法は言葉で教えられるだけでなく,書を繰り返し読むことで浸透していくものだからです。昔の作法書の重要性は繰り返し読むことができた点にあります。その昔は寺子屋で実語経を繰り返し読まされていました。大切なことです。
研究所で,デカルトの偉大さについて話しました。
デカルトは数を長さで表すことことを見いだした数学者です。この発見により,数学がとても把握しやすい学問になり,デカルト以降の数学は飛躍的に発展しました。
同時に,わかり易さが学生・生徒にも伝わり,400年の間にデカルトの発見を学校1年生,2年生でもしっかり理解できるところまで降りてきました。
デカルトの発見は,まさに算数・数学教育史も飛躍的に発展させたのです。
また,デカルトは「関係の関係」の把握には,記憶に残っている間に,最低3回の繰り返しが必要であることも見いだしました。
「座標」と「関係」,この2つは算数ソフトの「動き」に継承されています。その説明は省きますが,算数・数学が動くようになった今,デカルトの発見同様に,算数数学教育史はさらに歴史的に発展が進む段階に入りました。日本の算数・数学史のこの140年間は,大きな変化はあまりなく,さざ波,波打ち際程度の変化しかしていません。ほぼ横ばいが続いていたのです。それが終わり,上の学年の内容をどんどん理解していく時代へと進むようになります。
微積を小学校6年生が理解する日がそう遠くない日にやってくると言うことです。
研究所にいた皆さんは,かなり高いレベルで納得をしていました。
わずかな人数の納得でしたが,その様子を見て,私は「歴史が動く」と感じるほどの感動をいただきました。
立志尚特異 立志は特異を尚(たっと)ぶ,
俗流與議難 俗流は與(とも)に議し難し。
不顧身后業 身后(しんご)の業を顧(おも)わず,
且偸目前安 且つ目前の安きを偸(ぬす)む。
百年一瞬耳 百年は一瞬のみ,
君子勿素餐 君子素餐(そさん)するなかれ。
(『吉田松陰全集』山口県教育会)より)
安政5年(1858)の春,松下村塾に山田市之允(当時15歳)が入塾。それから2ヶ月ほどした6月,松陰が扇に書いて,山田に与えた詩です。そして,翌年の10月,松陰先生は獄死しました。
今は,NHKのドラマによるものか,かなり意訳された読みが広まっています。
立志尚特異 (志を立てるためには人と異なることを恐れてはならない)
俗流與議難 (世俗の意見に惑わされてもいけない)
不思身後業 (死んだ後の業苦を思い煩うな)
且偸目前安 (目先の安楽は一時しのぎと知れ)
百年一瞬耳 (百年の時は一瞬にすぎない)
君子勿素餐 (君たちはどうかいたずらに時を過ごすことなかれ)
(ウィキペディアより)
どちらにしろ,強い立志を促す力を感じます。
志が強いかどうかは,「リーダー」であるかどうかによると,私は思っています。どんな小さいグループでも,リーダーは何らかの方向性を考えざるを得ず,自然と志が形成されていきます。
その志が大きいかどうかは,「時流を見る力」によります。時代の寵児と言われる人は,やっぱり大きな流れを感じ取り,それに逆らわず,そこに自らの才覚を生かそうとします。流れに合わせるのですから,次第に志も大きくなってきます。
「百年は一瞬に過ぎない」と松陰先生が言っています。時代の行く先を見つめて,今をしっかり進むことです。ささやかですが,私の志も大きくなっています。

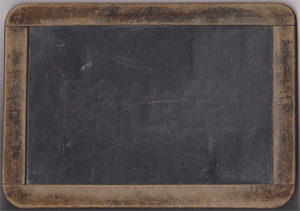
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















