次の火曜日,横浜市の小学校で授業をしてきます。
若い先生方を中心とした研究会があり,その研究会の一環として,5校時・6校時に授業をしてきます。
5校時は,6年生全員が対象です。体育館で「姿勢の良い人になろう」というテーマで授業をします。
6校時は5年生の一つの教室で算数です。図形の面積が終わろうとしている頃なので,そこに少し絡んだ授業をします。
授業の後は,若い先生へ向けた講話です。
どんな授業になり,どんな講話になるのでしょう。
明後日には詰めたいと思っています。
--
土曜日は野口塾in相模原です。
私も一こまお話しします。
テーマは「東アフリカ教育事情 算数ソフトの視点から」です。
楽しい話になりそうです。お近くの先生,ぜひお越し下さい。
--
 写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。
写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。
BLACK TEA というのは,紅茶のことです。
そのバングラデシュですが,私は「バングラディッシュ」と言っていました。
でも,どうも,違うようなのです。
フェイスブックで伊藤先生から「バングラデシュ」と普通は言うことを教えてもらいました。
ありがたかったです。
こういう指摘,年をとると,どんどん少なくなってきます。
だから,自分で気をつけないとなりません。
そんな状態が今なので,指摘してくれた人には手を合わせたくなります。
--
関連記事:
 算数ソフトの会議が開かれました。
算数ソフトの会議が開かれました。
日本でも授業で使って下さる先生が増えています。
子供達に喜ばれ,算数好きが増えています。
何ともありがたいことです。
会議では,バングラディッシュが話題になりました。
もしかしたら,3月までにバングラディッシュにも行くことになるかもしれません。
私が小学生の頃,バングラディッシュという国はありませんでした。あったのは西パキスタンと東パキスタンです。
インドを挟んだ東西にパキスタンが分かれていて,子供心に「すごい国だなぁ」と思っていました。
そうして,東パキスタンはバングラディッシュになり,国旗は日本によく似た図案になっています。
親日と思っていますが,今日はそういう話題にはなりませんでした。
算数ソフトが日本国内はもとより,海外からも注目されるようになりました。
こうなってくると,私もますます力が入ります。
海外の「子供達の学力向上」「先生方の資質の向上」に遠く日本から協力したいと思う気持ちがどんどん強まります。
一人の力では大したことはできません。
ですが,一緒にその道を歩んでくれる方々がいてくれます。
皆さんの力をいただきながら,「私も奮励したい」と思った一日でした。
--
関連記事:
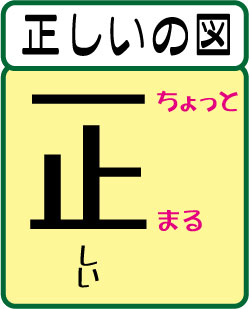 「姿勢の良い人になろう」という授業で,「自分に正しく,人に優しく」ということを「人と自分の図」を書いて話しました。
「姿勢の良い人になろう」という授業で,「自分に正しく,人に優しく」ということを「人と自分の図」を書いて話しました。
その延長の話を,懇親会で少ししました。
「正しい」についての話です。
「正」は,「一」と「止まる」に分解できます。
ですので,「一寸(ちょっと)止まって考えよう」と思っていれば,正しい判断ができるということになります。
カチンと来たときに,「ああ言えばこう言う」ですぐに返すと,けんかになりますが,ちょっと間をおけば,良い解決に向かえます。
どうしてこんな解釈をするのかというと,漢和辞典で漢字の意味を調べたからです。
「正」の一画目の「一」は,古くは「口」として書き城郭を表していました。
また,「正」から「征」が生まれています。
そうして,説文解字(せつもんかいじ)という中国最古の漢字字典には,正は「一以(もっ)て止まる」とあります。
映像が浮かびますね。
「軍隊が城郭に向かって進軍し,城郭の前で止まった」というようなイメージです。
進軍のまま攻めずに,いったん軍を止めて,どう攻めるか考えて軍を動かします。
そんなことを思っていると,自然と「ちょっと止まって考えると,正しい判断ができますね」となるわけです。
こういう話を知っていると,「正しさ」に関する授業をするとき,タイミングを見て話すことができます。
宇和島での授業では話しませんでしたが・・・。
--
関連記事:
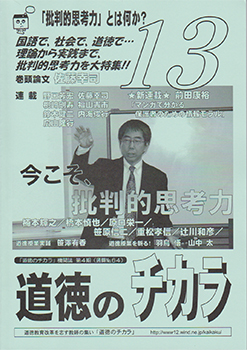 長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。
長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。
今回のテーマは「批判的思考力」です。
この『道徳のチカラ』は本屋さんでは売っていません。
私家版ですので,辻川先生に申し込みます。
いつも思うのですが,こういう活動を継続的に行っていることが素晴らしいです。
学生の頃,「歌集」を作ることが一つの文化になっていて,その延長線上で「冊子」づくりをする仲間がいました。
その影響もあって,私もこういうことをするのが好きでした。
ただ,継続する力が弱く,長続きはしませんでした。
表紙の一番下,タイトルのすぐ下の枠の中に,↓のように書かれています。
道徳教育改革を志す教師の集い「道徳のチカラ」
継続力は,この「志す」かどうかなのだと思います。
--
特集は「今こそ,批判的思考力」です。
もしかしたら昨年7月に出た,「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」への批判的思考力なのかなと思いました。「今こそ」と書いてあったからです。
でも,そうではありませんでした。
次号がそうなのかもしれません。期待しています。
--
関連記事:
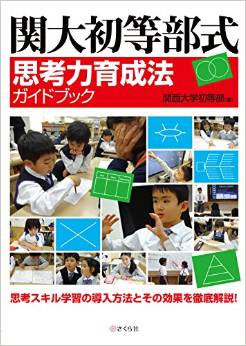 新年早々,「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループがフェイスブックにできました。
新年早々,「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループがフェイスブックにできました。
島原洋先生と会食を!
そんなところからスタートしたのですが,ありがたいことに島原先生は御同僚の先生と一緒です。
それなら,みんなで!となりました。
そこに三角えみ先生が加わり,これは楽しくなるなと思っていました。
そんなことをフェイスブックに書いたら,偶然にも読んでくれた先生がいて,あっという間に会食メンバーが増えました。
それを見て,三角先生が「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループをフェイスブック内に作ってくれたのです。
一緒に会食をする先生方をご紹介します。
島原洋先生(+同僚の先生方)
三角えみ先生
高本英樹先生
浅村芳枝先生
広山奈緒子先生
木村明憲先生
これに,篠原裕文先生が加わりそうです。
もちろん,私も一緒です。
合計8名(+α)です。
★持ち物:お弁当・飲み物
★場所:関大初等部の中のどこか
公開で勉強をして,会食交流で友だちを増やして。
午前中に見た授業の中で,一番グッと来たことを語り合ったら,楽しいですね。
こういうことができるのですから,SNSの発達は行動・交流に大きな影響を与えているとわかります。
当日が楽しみです。
公開当日,『ナマステ! 会いたい友だちと --友情は国境を越える』(著者:関西大学初等部6年生)が販売されます。これは外せないので,数冊購入してアクティブラーニングや世界貢献に関心のある方におわけしたいと思っています。
--
関連記事:
 「姿勢の良い人になろう」という授業をして,その内容を少し記しています。
「姿勢の良い人になろう」という授業をして,その内容を少し記しています。
昨日は,「ニワトリの図」を書きました。
ニワトリさんやお猿さんたちと,人はちょっと違うんだという話です。
「良い・悪い」がわかるのが人なんだと言うことです。
「良い・悪い」があることの話をしたら,ついでに「分別がある」の話をすることができます。
「分別」は「ふんべつ」です。「ぶんべつ」と濁ると,ゴミの分別になってしまい,話が進みません。
「分別がある」というのは,まさに読んで字のごとしです。
「分けて」「別れる」のです。
何を分けるのでしょうか。
「良いと悪い」を分けるのです。
何と別れるのでしょう。
悪い方と別れるのです。
物事に良い悪いがあり,その「良いと悪いを分けて」,「悪い方と別れる」のが分別があるということなのです。
食事の仕方にも良いと悪いがあります。
姿勢にも良いと悪いがあります。
挨拶の仕方にも良いと悪いがあります。
要するに,礼儀作法の世界には良いと悪いが必ずあるのです。
「悪い方と別れるぞ」と判断できる人が分別のある人です。
「悪くてもいいや」と判断する人は分別のない人であり,場合によっては聞き分けのない子なのです。
こういうことを知っていると,時間があれば,「良いと悪いを分けて,悪と別れる」とみんなで唱和したくなってきます。
漢字を訓じることで,道徳の指導に大いに役立つことがあります。
そんなとき,「日本語は素晴らしいな」「漢字はありがたいな」とつくづく思います。
--
関連記事:









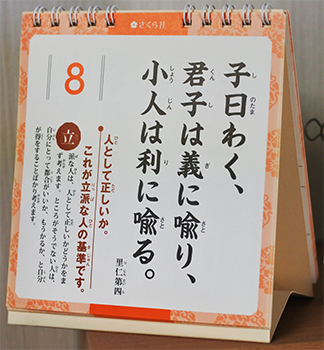



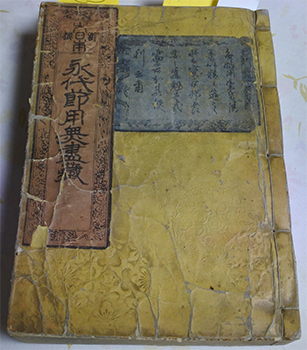
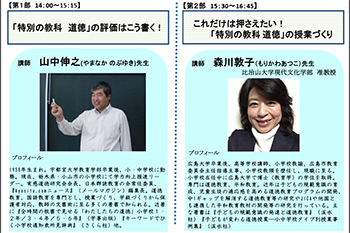


![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















