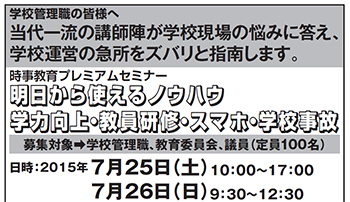 ごっついイベントがあります。
ごっついイベントがあります。
時事教育プレミアムセミナーです。
テーマが,いいですね。
「明日から使えるノウハウ
学力向上・教員研修・スマホ・学校事故」
セミナーは,7月の25日(土)と,26日(日)の両日開催されます。
学力向上,教員研修が気になるので,25日に参加する予定です。
25日には,大槻達也氏,貝ノ瀬 滋氏,近藤昭一氏の講演があります。
楽しみです。
午前中からの開催ですので,何とか朝から受講できるようにしたいと思っています。
会場は銀座です。
--
 ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。
ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。
PCというのは,日本では「パーソナルコンピュータ」といいますが,長いので「パソコン」といいます。また,「ピーシー」とも言います。
こういう略称は,ケニヤにもあり,PCは「ピースィー」だそうです。
発音の違いという程度で,なるほどと思いました。
さて,「3kg」と書いてあったら,日本では「3キログラム」と言い,略して「3キロ」です。
これが,ケニヤでは「3ケージー」なのだそうです。
頭文字で略するのです。
世界の機構などが頭文字で略されていることは知っていましたが,こういう日常語も頭文字で略しているようです。
国際化がどんどん進んだら,国際派の先生も増えていき,国際的な略称も教える先生が出てくるかも知れませんね。
--
明後日は,大阪の野口塾です。
中嶋先生の講座もあり,賑やかな一日になりそうで,今から楽しみです。
--
写真は,大船の観音様。駅からつながっている歩道橋から見えます。いいお顔ですね。しばし,拝みました。
--
関連記事:
教えてくれたのは,実力者の浅村先生です。
学力向上指導教員が6年生の授業を参加したそうです。
その時,6年生の先生は,浅村先生に勧められて,この円を転がす算数ソフトを使いました。
そうしたら,指導教員から「ソフトがいい」と褒められたそうです。
もちろん,指導された先生の指導力も褒められていますが,ソフトも褒められ,とても嬉しい気持ちになりました。
--
少々,このソフトについて,お話をしましょう。
「円周率」を学ぶ場面で使うソフトです。
円周率は3.14と覚えてしまえば,それで良いのかも知れません。でも,小学校は,そんな暗記ですますようなことはしません。
1,どうして「3.14」になるのか。
2,「3.14」とは何と何の関係のことか。
こういう大事な思考の学習を,しっかり学習します。
授業では,円を転がして「直径」と「円周」の関係を学びます。
工作用紙に描いた円を切り抜いて,実際に転がして・・・と授業をします。
ところが,人力ですので,どうしても誤差が出ます。
また,実際に転がす操作をするので,転がすところにエネルギーがそそられ,「直径」の数値と,「円周」数値とを見比べて考えるという,一番大事なところに力が入りにくくなります。
このソフト。転がる様子を見ることができるので,ちょっと俯瞰して概念を把握できます。
さらに,ボタンをクリックすると,物差しに直径で幾つ分になるのか,示されます。
1cmの円でも,2cmの円でも・・・・10cmの円でも,どれも「直径が3つとちょっと」になることを見ることができます。
10個もある円で,いつでも3.14になっていることを確かめたら,円周率というのは,「直径と円周の関係」であり,「どの円でも直径の3.14倍が円周!」と伝わってきますね。
浅村先生からのお知らせメールで,とても元気を頂きました。
算数ソフト,これからも,少しずつですが,紹介していきます。楽しいですね。
--
関連記事:
わずか6行の事ですが,その力量に圧倒されます。
「文学読書会」というのは,保護者との読書会です。テキストとなるのは,文学の有名な本。
それを毎月1回,開催していました。
野口先生の読解力,鑑賞力のすばらしさは,こうした素養にあるとつくづく思います。
ですから,何度,セミナーに参加しても,新鮮な驚きを感じます。「深い」という言葉でしか形容できない,自分が恥ずかしくなります。
27日の野口塾で先行販売されました。
その時,手にした熊谷先生が,すてきなコメントをかかれていました。
「『教師の覚悟』先行販売で手に入れる事ができました。
それにしても,松澤先生のお仕事には言葉もありません。」
松澤先生は,この本の編著者の先生です。現役の校長先生です。
よくぞここまで,野口先生の御論文を収集し,読みこなしたものだと痛感します。
惚れ込むだけでなく,歴史に残そうと仕事をされました。
感動しています。
7月4日の流し素麺野口塾で,松澤先生とお会いします。
松澤先生のサインをいただけるます。楽しみです。
今度の土曜日は,大阪の「授業道場野口塾IN大阪」に参加します。
私も一こまお話をします。
「最先端!算数ソフトと事前学習」です。
--
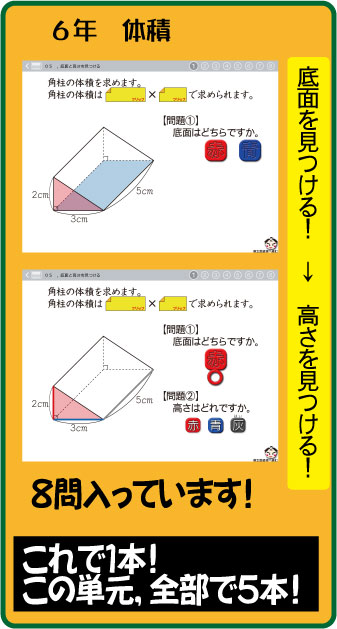 算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。
算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。
6年生の「体積」から1本,ご紹介します。
体積の求め方として,「底面積×高さ」を学習します。
この考え方はとてもありがたい表現です。
なにしろ,底面の形がどう変わろうと,すべて「底面積×高さ」と表現できます。
柱状の立体なら,どんな形をしていても,「底面積×高さ」なのです。なので,「公式」となっています。
たいへん,ありがたい公式なのですが,立体を見て底面がどこなのか,正しく指摘できな子もいます。
これは,立体の底面を見つける経験が不足しているだけのことです。
もし,底面を間違えそうな子がいたら,「05 ,底面と高さを見つける」のソフトを使ってみてください。
立体の見取り図を見ながら,
「底面を見つける」→「高さを見つける」
この学習を8問も連続してできます。
8問も練習をしたら,立体の底面を見分ける目ができてきます。
--
この「底面積×高さ」は,中学へ進むと「V=Sh」と横文字になります。
非常に簡略になるので,図を書いても文字がじゃまになりません。
こういう点では,アルファベットはシンプルでいいと思っています。
このVは,ボリューム。volume。
Sは,サーフェイス。Surface。
hは,ハイ。Height。
マイクロソフトが作った薄型のPCの名前がサーフェイスだったので,このSが少し日本語化し,意味を理解しやすくなりました。
6年生での学習では,時々,「中学へ行くと・・・」と話をするのもいいです。
--
関連記事:
群馬で野口塾が開催され,会場で『教師の覚悟』が先行販売されました。
「今,買いました」と嬉しいニュースがフェイスブックにも飛んできました。
ありがたいことです。
発売は7月7日ですので,まだ,もう少し日数がかかります。
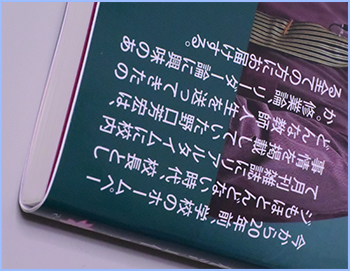 『教師の覚悟』の表紙。
『教師の覚悟』の表紙。
帯に少々小さい字で記されているところがあります。
ちょっと,クローズアップしてみました。
20年前。
確かに,ホームページもよちよち歩きでした。
重い画像があると,少しずつしか表示されず,しばし待たされたものでした。
そんな時代に,すでに校内のことを雑誌にアップしていたのです。
先見の明ですね。
来月の11日は,野口先生の御自宅で,流し素麺の野口塾が開催されます。
一度は野口先生の御自宅へ行ってみたいと思われている先生,お申し込みは少し早めが良いです。
人気があり,毎回,満員です。
私は流し素麺の日に,サインを頂こうと思います。
--
関連記事:
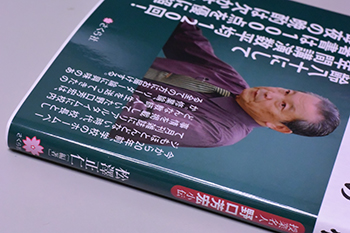 野口芳宏先生の『教師の覚悟』(松澤正仁編著)の背表紙と裏表紙です。
野口芳宏先生の『教師の覚悟』(松澤正仁編著)の背表紙と裏表紙です。
背表紙には,野口先生のお名前といっしょに,愛媛の松澤正仁校長先生のお名前が示されています。
ジーンと来ます!!
裏表紙には,若かりし頃の野口先生のお写真が。
夏の暑い日だったのでしょうね。ネクタイをきちんと締めて御講演をされています。
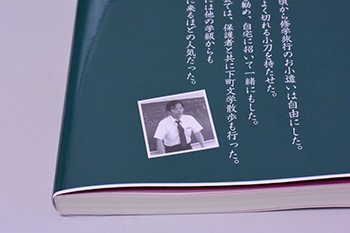 野口先生の後ろの黒板に書かれている文字が少し読み取れます。
野口先生の後ろの黒板に書かれている文字が少し読み取れます。
「抵抗と限界」
どんな話だったのか,聞いてみたくなります。
裏表紙には若い頃の担任時代のエピソードの一端が記されています。
◎お小遣いは自由にした。
◎小刀を持たせた。
子供達に考える力,実行する力をつけていく実践です。
今日は,群馬で野口塾です。主催されている塚田先生のお姿も,この本のどこかの写真に載っています。そこに私も写っています。
発売は7月7日です。楽しみですね。
--
関連記事:

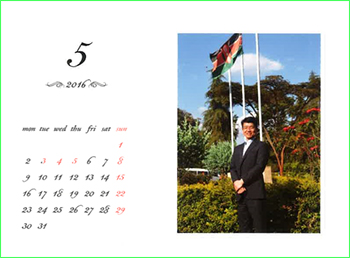
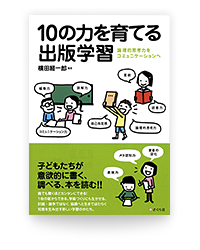


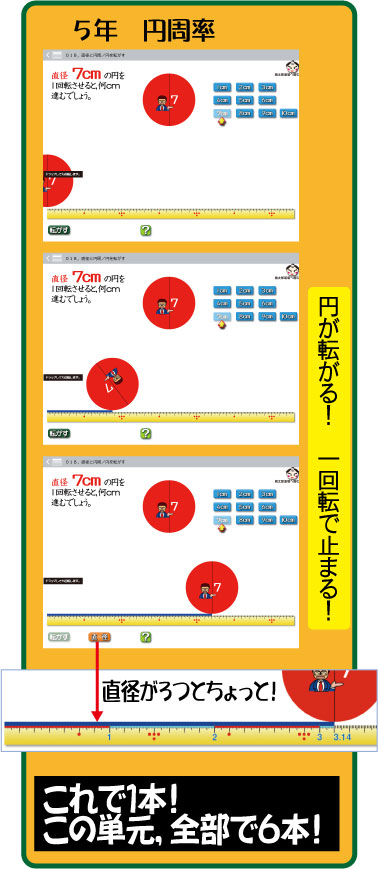



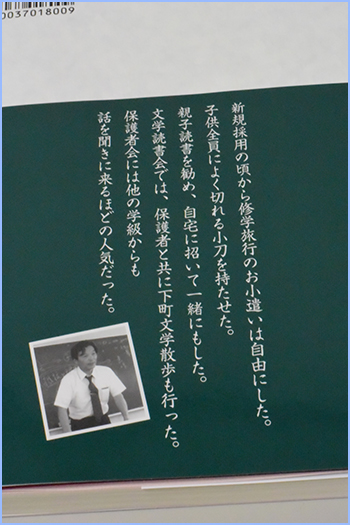





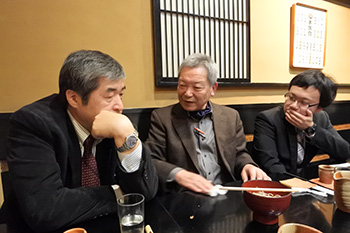

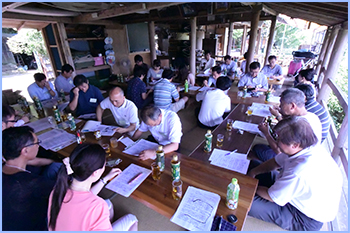
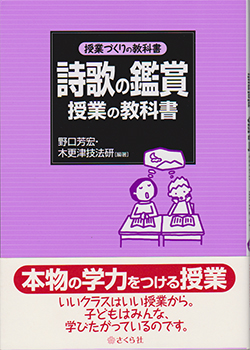
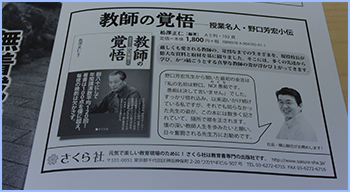
![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















