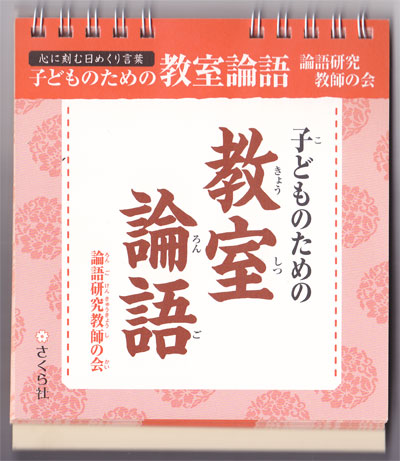 お正月なので,『論語』(吉川幸次郎著,朝日新聞社)を読み返しています。
お正月なので,『論語』(吉川幸次郎著,朝日新聞社)を読み返しています。
滑り出しは「学而第一」。
1,学びて時に之を習う,また説ばしからずや。
2,友あり遠方より来たる,また楽しからずや。
3,人知らずしていからず,また君子ならずや。
自分の勉強は「1」のごとく。
自分のことなので,これは専門的に勉強を進めていけば,自然とこうなります。
「1」のように勉強したからと言って,「2」となるかは怪しいです。
自分の勉強が人のお役に立ってこその,「2」です。
「1」「2」を自覚したら,そこから先は修養です。
自分のことを知らない人がいて,それで普通なのだと思える気持ちでいることです。
論語は,こんな風に,自分の頭や心を少し良い方向に向けてくれます。
今年は,還暦を迎えます。
ですので,「為政第二」で,しばし過去をふり返りました。
1,吾れ十五にして学に志す。
2,三十にして立つ。
3,四十にして惑わず。
4,五十にして天命を知る。
5,六十にして耳従う。
6,七十にして心の欲する所に従って,のりをこえず。
大筋,こんな感じに人生を歩んでいます。
特に,「五十にして天命を知る」は,ほぼドンピシャです。
算数ソフトを作ることが,私にできる最大の世の中への貢献。こう思えた頃です。
そうして,六十を迎える今。「耳従う」とはよく言ったものです。
作った方が良いと自分で考えたところをソフト化する段階は,ほぼ終わりました。
次第に,算数ソフトを使ってくださる方々の声を聞いて,それを作る傾向になっています。
御要望に応えつつソフト開発をする。それが妙に嬉しい自分になっています。
今作っている一本を作り終えたら,クラウドに中学一年のソフトを入れられるようにしていく予定です。
ちょっと,長丁場の作業になりますが,これも「耳従う」の流れです。心地よく前進できます。
『論語』や『大学』などを教室で素読学習している先生もいます。
青森の駒井先生はその道の先達です。
写真の論語は,日めくり論語です。
これを先生の机の上に置いている先生もいます。
月日が経つと,子ども達が変わってくると聞いています。
元旦に『論語』を少し読み返せて,今年も穏やかな良いお正月となっています。
野口芳宏先生からお電話をいただき,12月10日(火)は木更津技法研に参加することになりました。
私と同世代の多田元樹先生が県の教育功労賞を受賞されたので,その祝賀会を開催するそうです。
技法研に関わった先生方が集まるのですから,レポートも登場する祝賀会になるのではないかと思っています。
--
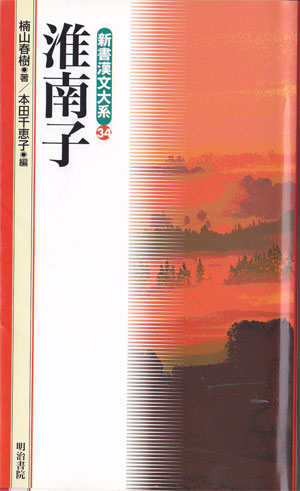 東京に出るその道中は基本的に読書です。
東京に出るその道中は基本的に読書です。
先週末は,久々に『淮南子』を読みました。
淮南子と言っても,ピンと来ないと思いますが,人間万事塞翁が馬のお話しが載っている中国の古典です。
紀元前140年頃に記されたそうです。
今回読み返して,「あっ,すごい!」と感心させられたのは,「君が道を知るについては,やはりこつがあるのかね」との下りです。
普通に読み下し文だけを読んでいると,ラインを引いたり,付箋を貼ったりするほどの所ではありません。サラッと読み流してしまう所です。
今回は,ちょっとゆったりとして,楠山春樹先生の記された背景も楽しみながら読んでいました。そうしたら,目を見張る解説がされていて,思わず膝を打ちました。
それから,その前後を夢中になって読み返し,ハッと前を見たら,降りる駅でした。
この本は,淮南子が抜粋されて載っている本なので,できれば,全文を読んでみたいと思い,新釈漢文大系の淮南子(上)を注文しました。著者は同じく楠山春樹先生ですので,注釈におおいに注目しながら,読み進めたいと思っています。
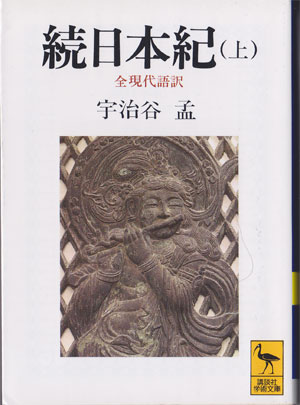 『続日本紀』を読んでいます。
『続日本紀』を読んでいます。
日本書紀の続編の正史です。
日本書紀も面白いですが,これも思っていた以上に面白いです。
まず,グッと来たのは博打はダメだったということです。
「博打や賭けごとをして,遊び暮らしている者を取り締まった。」
いわゆる遊び人は昔もダメだったのです。生活を崩すこともありますが,生産をしないでも過ごせることに甘んじるその精神の堕落が,世の中に悪影響を及ぼしていたのだろうと思います。
唐の人が見た日本人観も出ていました。
「唐人がわが使者に言うには『しばしば聞いたことだが,海の東に大倭国があり,君子国ともいい,人民は豊かで楽しんでおり,礼儀もよく行われているという。今,使者をみると,身じまいも大へん清らかである。本当に聞いていた通りである』」
魏志倭人伝にも,穏和で争いを好まず,礼儀正しい事が記されています。
相手を思いやる心,目上を大切にする心といった,日本人にとってはごく当たり前のことが珍しいのかもしれません。敬語と礼儀作法が高い水準で保たれているのは,国の大きな顛覆が無かったからだと思います。それが何よりありがたいと思います。
その礼についても,詔が下されたことが記されていました。
「そもそも礼というものは,天地の正しい法であり,人間の生活の手本である。道徳や仁義も礼によって初めて広まり,教訓や正しい風俗も礼がそなわることによって成就する。」
これは,まさに儒教です。仏教が広まっていた時代ですが,儒教を捨てずに仏教を吸収しようとしています。優れた新しい文化をこれまでの文化の中に上手に取り込んでいく日本人。たいしたものです。
途中まで読み進めて,どうしても,気になる言葉と遭遇しました。
今読んでいる本は現代語訳ですので,実際にどういう言葉で記されていたかは,よく分かりません。読み下し文が載っている本でその言葉を確認したいので,それを注文しました。
--
中学2年の「一次関数とグラフ」のソフトを作りたいと思っています。比例を習った子が見たら,ナルホドと思えるぐらいのソフトになればと思っています。
持っていた本居宣長の本に「古事記伝」の総論が載っているので,そこを読みました。
驚きの研究者です。
日本書紀と古事記は,日本人として読んでおかないとならない書と思っています。
でも,その中身がどうのと,研究者のように読む必要もないので,好きな算数や作法の世界がちょこっと顔を出すところを見つけては楽しんで読んでいました。
古事記や日本書紀の話しになると,たいていの人は古事記の方が面白いというのですが,それがどうしてなのか,よく分からずにいました。私には,日本書紀の方がとっても面白いと感じられているからです。
どうして日本書紀の方が面白いと感じるのかは,自分でもよく分かっていません。
でも,「古事記伝」を読んで,その理由が少し分かった気がしました。
日本書紀には儒教や仏教の考えが入り込んでいるということが,よく分かったからです。
儒教は作法の根本的な存在なので,それが私を惹きつけているのです。
こうわかってくると,もう一度,日本書紀,古事記を読み返したいと思います。
「古事記伝(総論)」を読んで,「まことの日本」の意味が少し分かってきました。
時間をおいて,「古事記伝」の中身も読み進めてみたいと思っています。そうして,「まことの日本」を感じてみたいです。
そうそう,「古事記伝」を読みつつ,宇佐美寛先生がダブってしまいました。
日本書紀・古事記のここがダメだと明確に指摘し,その根拠も記しているからです。
引用の仕方も宇佐美先生と同じです。
江戸時代が本居宣長なら,今の時代は宇佐美寛先生です。
河合隼雄先生の『こころの最終講義』を読んで,読書熱が高まり,今日は本居宣長の「玉勝間(たまかつま)」を読みました。
何度読んでも,ズシンと響いてきます。
それは,学ぶ人の学ぶ姿勢がしっかりと記されているからです。
◎未熟な学者が,心はやって唱え出す新説は,一途に「他人より優れよう,勝とう」という気持ちで,軽率に,前後を十分に考え合わせずに・・・・
戒め的に,自分に降りかかってきます。
◎だいたい旧説は十の中で七つ八つの点は悪いのも,その悪いところをおおい隠し,僅かに二,三の用いるに足る点があるのを特に持ち上げて,出来る限り援護採用する。新説は十のうち例え八つ九つの点はよくてみ,残りの一つ二つの悪い点を特に批判して,八つ九つの良い点をも抹殺し・・・・
新説を唱えるときに,何に留意すべきか,示唆多いところです。
こういう内容がビッチリ載っています。
天狗にならないように自分に語りかけるに,ちょうど良い書です。
本居宣長と言えば江戸時代の国学者です。
まことの日本を愛し,研究した人です。
そのまことの日本は何かというと,これは「玉勝間」を読んでも分かりません。
古事記と万葉集を読まないと分からないのです。
その学びには,本居宣長の「古事記論」は読んでおかないとなりません。
「古事記論」までは踏み込む予定はなかったのですが,学びにも勢いというものがあります。
明日から読み進めてみようと思っています。
昨夜遅く,久しぶりの雷となりました。
万一に備えて,データの入っている外付けハードディスクをPCから切り離しました。
これで,一安心。
--
そうして,『風土記』です。
ようやく「肥前国風土記」に入りました。
肥前,肥後の「前」「後」の意味も書いてあり,多いに勉強になります。
ちょっと,思いにふけったのは,崇神(すじん)天皇(第10代天皇)の命を受け肥後の国へ討伐に行った健緒組(たけおくみ)が,戦勝報告をしたセリフです。
「臣(わたくし)は,かたじけなくも大君の命令を受けて・・・・討伐をすると,刀の刃を血ぬらずに・・・・凶賊どもは自滅いたしました。
大君の御威光によらなかったら,とうていそのようなことはありえなかったでしょう」
実際にはどろどろとした戦いになっていたのだと思いますが,それをそのまま正確にかくかくしかじかでしたとは,報告していません。
目の前にいる大君が喜ぶように,大君を立てるように伝えています。
しかも,まるで奇跡が起こったかのように伝えています。
こういう報告の仕方,ここに日本人の報告作法の原点があるように感じました。
また,健緒組の使った刀は,崇神天皇からの拝領刀のようにも思えています。
超高級な刀なので光をまばゆいばかりに反射します。晴れた日に敵と対峙したら,神々しい力が剣から放射されたようにも思います。
当時のハイテク技術で戦い,報告は日本人的に。そんな姿が感じられ,風土記がますます面白くなっています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















