 私と一緒に,良い姿勢の普及に努めている渥美清孝先生。
私と一緒に,良い姿勢の普及に努めている渥美清孝先生。
シンポジウムでも,凜としています。
この姿勢で考えるから,良い方向へと思考が進みます。
渥美先生は,猛暑の午後2時から始まったシンポジウムの時間,ずっと,この姿勢を保持し続けていました。
西洋伝来の背もたれは,背を休めるときにのみの利用です。
日本人たるもの,こうあるべきです。
この日の懇親会で,渥美先生は鍛える国語研究会の重責を担ってほしいと先輩から頼まれていました。
「姿勢がよいと,信頼が高まり,
信頼が高まると,担う仕事が増えていく」
その様子を目の前で見た感じでした。
頼まれた仕事を通して,次第に人格も磨かれていきます。
渥美先生は,善良なスパイラルの中に位置しています。
見習いたいものです。
--
「作法」について,昨日,講演を・・・と,お話をいただきました。
来年の1月に開催される野口塾in木更津で,一こま,私が作法の話をします。
シーズンを考えると,卒業式に向けて・・・という感じがしています。
話す内容は,基本的に同じですが,何度も何度も話すことが大事なので,私も元気に話ししたいと思います。
また,今月の30日(土)に,東京の小石川大神宮で「お行儀」の話をします。
小石川というのは,時代劇などでよく出てくる小石川療養所のあったところで,
小石川大神宮は東京ドームの近くにあります。
こちらは,親子向けの話になります。
2学期が始まる直前なので,そこも含めながらの話になると思います。
渥美先生のように,自分の上体を自分で支えられる,しっかりした人物に育ってほしいと願いながら,話をしてきたいと思います。
鍛える国語研究会(略称は「鍛国研」)の第6回全国大会が,千葉県の袖ヶ浦市立昭和小学校で開催されました。
近くなので,会員の先生方の活躍ぶりを見学させていただきました。
驚いたのは,柳谷先生の授業でした。
まずは,出身の北海道の話です。子ども達はぐいぐい引きつけられて,「いいなぁー!」など,柳谷ワールドに引き込まれました。
 その後,グイッと引き締めるように,姿勢の指導がありました。
その後,グイッと引き締めるように,姿勢の指導がありました。
腰骨を立てる「立腰」の話をささっとされました。
子ども達の姿勢は一気に良くなり,教室が凜とした雰囲気になりました。
それから国語の授業です。
この暑さの中の子ども達です。教材文を読み,問題を考えている内に,姿勢は崩れていきました。
そんな中,教室の後ろの方にいた男の子1名,女の子1名がずっと良い姿勢をし続けていました。しかも,授業中,ずっとです!
私は嬉しくなり,授業後,二人の所へ行き,ちょっとインタビューをしました。
家で何か習い事をしているのかと尋ねたら,女の子は「ダンスを習っている」と応えてくれました。
なるほど!と思った次第です。
男の子は,「何も習っていない」と言い,姿勢については「家では特に言われていない」と話してくれました。
不思議に思い,「どうして,1時間,ずっと良い姿勢でいたの?」と尋ねました。
すると,男の子は,「柳谷先生に,教わったからです」と答えてくれました。
実に感動的でした。
柳谷先生は,さらりと姿勢指導はかくあるべしと示してくれていたのです。
ありがたい授業でした。
--
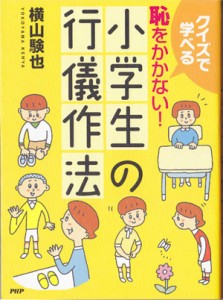 PHPから出している『小学生の行儀作法』が5刷りになるそうです。
PHPから出している『小学生の行儀作法』が5刷りになるそうです。
生協だけの販売なのですが,なかなかよく検討しています。
「作法」の基本は,やっぱりなんと言っても「姿勢」です。
特に,いすに座ったときの姿勢です。
いすに座って,姿勢を良くすると,背もたれから背中が離れます。
「自分の上体を自分で支えている」状態になります。
この姿,実に凜として格好良いです。
逆に,背もたれにもたれた姿。
自分を自分で支えられない姿です。
それがずっと続くのは,すっごく格好わるいです。
姿勢は,時代劇を見ていると面白いです。
主役は,キチッとした良い姿勢をしています。
主役の仲間は,正義の心を持っていますが,体が今一歩です。
悪役は,体が斜めになりやすいです。
時代劇は役作りをし,演じられている姿です。
「作られている姿」なので,そこには強調が入り込みます。
「主役=格好良い=姿勢正しい」と強く結びついてきます。
良い姿勢はやっぱり格好良いのです。
この夏は,幼稚園の先生,小学校の先生に作法の話をしてきました。
今週末の広島県福山市で開催される「第22学 教師力向上セミナー」でも,作法の話をします。
そうして,立志舎さんプロジェクトで,8月末に「神社」で作法の話をしてきます。
「神社」というのは,人々の集うところです。
神様もいる集いの場です。
良いことを指向するのが,当たり前の場なのです。
神社で作法の勉強ができる子は,良いですね。
大 分の古城校長先生のお計らいで,たくさんの幼稚園の先生方の前でお話をすることができました。
分の古城校長先生のお計らいで,たくさんの幼稚園の先生方の前でお話をすることができました。
前日に,古城校長先生と一献傾けました。
幼稚園の工藤先生,是永先生,芦刈先生もご一緒で,ディズニーランドや赤ちょうちんなど,あれこれ楽しい話題で盛り上がりました。
途中,工藤先生を中心とした幼稚園での実践談に耳を傾けました。小学校とは視点がちがい,大いに勉強になった次第です。
当日は,「幼児期に必要な算数の概念と礼儀作法」の話をしました。
算数では,「指折り数える」ことを幼稚園の先生もご指導されていますが,この中に「習慣は第二の天性」という大事な要素が含まれていることを話しましました。
実際に指を折ってもらい,先生方が会得している「第二の天性」を体感していただきました。
かなり,高いレベルで納得をしてくださっていました。
こういう「第二の天性」が連続的に起こっているのが算数なのです。
そういう大きな流れのところまではお話ししたかったのですが,それには具体をもっと出さないとならず,とてもそこまでは語れませんでした。「第二の天性」というのは,見方を変えると「否定の否定」となります。
また,算数の力の分かれ目は,「数詞・数唱・物」の3つを同時に示せるかどうかにかかっていることを話しました。
この考え方は,算数ソフトという新しい教材の出現により,かなり明確になったところです。
途中から,作法の話をしました。
割り箸を使って,箸の取り方・置き方をやったら,9割ぐらいの先生がきちんとできていて,こちらがびっくりしました。
幼稚園の先生は,基本的作法の達人集団と感じた次第です。
--
壇上から先生方を見ていて,さすがだなぁと思ったのは,メモをどんどんとっていることでした。
後で,古城校長先生に聞いたら,エプロンのポケットにはメモ帳が入っていて,そこに随時メモをとるのが,大分の幼稚園の先生方なのだそうです。
平素のメモ力が,こういう場でも自然と出ているのだそうで,この気風に脱帽しました。
--
是永先生が,車に温泉グッズを入れていると言っていたのが印象的で,当日の控え室でそんなことを話したら,「私も入れている」と言われ,これまた驚きました。
--
工藤先生から聞いた「しんけん」という大分方言。「しんけん雨が降っている」と使います。「たくさん」と意味だそうで,それを公演中に話を交えたら,「そうです」という雰囲気になりました。「しんけん驚きました」となりました。
火曜日に大分県の幼稚園の先生方の研修会があり,そこでお話をしてきます。
「県幼会夏期講習会」と呼ばれている研修会で,県内の国公立幼稚園の先生方を中心に100名以上が集まります。
私の演題は,「幼児期に必要な算数の概念と礼儀作法」です。
演題通り,算数から入り,作法で終わる予定です。
今日は,その準備をしていました。
算数では算数ソフトを使います。
作法では,割り箸を使う予定です。
当日,私はステージの上で話すそうです。
得意の机間巡視ができません。
スクーのように,淡々と話し進める感じになりそうです。
材料がそろっていると,淡々と話しても,机間巡視をしても,どっちでも楽しい雰囲気になります。
夏の暑さを吹き飛ばす,講習会になればと願っています。
--
スクーですが,「横山験也の算数の授業 第2回」に,「受けたい!」をクリックした方が,42名になっています。
ありがたいです。
1回目もなかなか面白かったですが,2回目もかなり良い感じになると思っています。
27日(日)の午後11時,お時間のある先生,ネットでご覧ください。無料です。
--
 話は変わりますが,宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンですごいです。
話は変わりますが,宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンですごいです。
今見たら,1365位でした。
表紙もすごいですが,中身はもっとすごいです。
宇佐美先生の『私の作文教育』が,御茶ノ水駅近くにある「日本製紙グループ お茶の水ペーパーギャラリー」に展示されました。
夏休み中に,行ってみたいと思っています。
『私の作文教育』,8月2日の『道徳のチカラ』のイベントでも販売になる予定です。
この夏は,宇佐美先生と共に熱くなりそうです!
まだの先生,是非お読みください。
8月2日(土) 「第22学 教師力向上セミナー 授業づくり今、むかし~ICTと作法・和算~」です。
算数ソフトの話に加え,今,盛り上がっている「事前学習法」についても,少しお話をします。
近場の先生,ぜひ,足をお運びください。
7月27日(日)は,スクーです。なんと,「受けたい!」が18になりました!
そうして,9月6日(土)は,教育の原点セミナーです。「国語科教育 原点から実践まで」です。
楽しみが一杯です。
--
 戦前の行儀作法を調べていくと,避けて通れないのが,奉安庫・奉安殿です。
戦前の行儀作法を調べていくと,避けて通れないのが,奉安庫・奉安殿です。
御真影と教育勅語を奉りつつ安置しておく場所です。
関連本を読んでいると,奉安庫などの名前がでてくるので,保管庫があることはわります。
ですが,それがどんな風になっているのかは,活字からはわかりません。
奉安庫の他に,奉安殿というのもあり,ちょっと気になっていました。
そうしたら,偶発的に,ヤフーオークションに当時の記念絵はがきが出ていることを知り,早速,1つ落札しました。それが,この写真です。高等小学校の奉安殿です。
かなり大きいです。
屋根は切り妻。両サイドの千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)が,いかにも・・・という雰囲気です。
当時は,この前を通るときは一礼をしていました。神社の前でも一礼をしていました。
このような神聖とされる場所が,戦前の小学校には普通にありました。
今の学校には,このような神聖な場は無くなりました。
でも,家庭の神棚や仏壇が,そっとその神聖さを伝えてくれています。
家庭での神聖な場は,教育上,とても重要です。
核家族になり,御両親の力だけでは子育てが厳しくなりつつあります。
そんなとき,思わぬ力を発揮してくれるのが,神棚や仏壇なのです。
中嶋先生と,野口塾でこれに関連した話をしました。
学級経営の基本「天地人」の「天」です。
大事にしたいところです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















