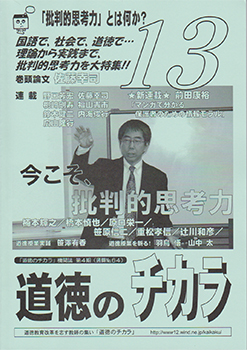 長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。
長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。
今回のテーマは「批判的思考力」です。
この『道徳のチカラ』は本屋さんでは売っていません。
私家版ですので,辻川先生に申し込みます。
いつも思うのですが,こういう活動を継続的に行っていることが素晴らしいです。
学生の頃,「歌集」を作ることが一つの文化になっていて,その延長線上で「冊子」づくりをする仲間がいました。
その影響もあって,私もこういうことをするのが好きでした。
ただ,継続する力が弱く,長続きはしませんでした。
表紙の一番下,タイトルのすぐ下の枠の中に,↓のように書かれています。
道徳教育改革を志す教師の集い「道徳のチカラ」
継続力は,この「志す」かどうかなのだと思います。
--
特集は「今こそ,批判的思考力」です。
もしかしたら昨年7月に出た,「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」への批判的思考力なのかなと思いました。「今こそ」と書いてあったからです。
でも,そうではありませんでした。
次号がそうなのかもしれません。期待しています。
--
関連記事:
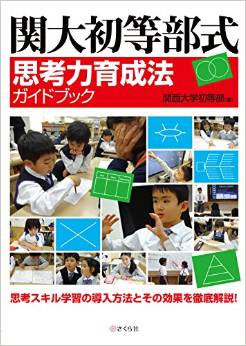 2月6日(土)の関大初等部の公開。
2月6日(土)の関大初等部の公開。
申し込みをすませました。
公開授業①は3年2組のMUSE学習。
公開授業②は4年2組の算数。
公開授業③は6年1組のMUSE学習。
教科等協議会は4年2組の算数。
MUSE協議会は6年のMUSE。
ここまでが自由選択です。
他にも2つ,ナイスな展開があります。
鼎談:「教科教育から見たミューズ学習の価値」
シンポジウム:「思考スキルを診る~授業デザインを省察するために」
久しぶりの参観になりますが,とても楽しみです。
--
公開の日のお昼は,島原先生,三角先生と一緒です。
こちらも楽しみです。
--
関西に行ったら,一度,お会いしたいと思っている社長さんがいるので,連絡をしました。
調整してくれて,前日の夕方,京都でお会いすることになりました。
5日,6日と楽しいことが続きます。
--
関連記事:
 「チーム算数」に鹿児島の蔵満先生が参加。
「チーム算数」に鹿児島の蔵満先生が参加。
他に,いつもの城ケ崎先生,佐々木先生と私。
面白いひとときになりました。
蔵満先生は,小学校の先生になる前から,「50歳で退職」と人生設計をしていました。
それをほぼきちんと実行して,今はエッセイやクイズ,教育の執筆活動へ転身しています。
人生設計通りの歩み,たいしたものと思いました。
今年は,退職の1年目。
行きたいと思っていたところへ足を運んでいます。
その行きたいところが,観光地ではなく,「気になる先生の教室」です。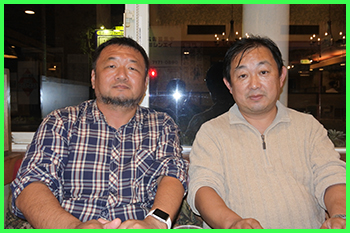
これは,実にすばらしい行動です。
たいていの場合,退職前までそう思っていても,実際に退職をしたら,教室見学をする意味を見いだせなくなります。
思いはあっても,実行はされず,次第に教育から遠ざかります。
教室見学の流れで,昨日は城ヶ崎先生の教室を1日見学したそうです。
授業を見に行く蔵満先生もさすがですが,それを歓迎する城ヶ崎先生もナイスです。
佐々木先生からは,アプリの情報提供がありました。
毎回,新しい面白い教育ソフトを教えてくれます。まさに,「アプリ通」です。
この能力,これから先,大いに求められるところです。
アプリ探しで行き詰まったら,佐々木先生に問い合わせてみるのもいいですね。
私は,来春発売の「単元別中学数学ソフト」の一部を紹介しました。
正の数負の数と方程式をすこし見てもらいました。
6年の3学期に総復習の問題がてんこ盛りで出てきます。
その時間を少し減らして,中学1年の内容をソフトでザザッと見せておいたらどうなるでしょう。
ほぼ間違いなく,中1の数学がとてもわかりやすくなります。
「事前にソフトを見ておく」
これが算数・数学をわかりやすくする秘訣です。
鹿児島に行くときには,蔵満先生に声をかけて,またゆっくり話したいと思います。
--
関連記事:
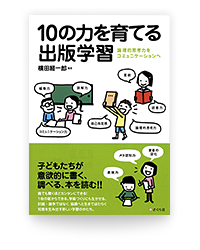 メルマガ「ぼうけん」が,発行されました。
メルマガ「ぼうけん」が,発行されました。
719号です。
編集長は山本校長先生です。
今,発行部数を見たら,1,206部もありました。
今回の号も内容が濃かったので,読者の先生方にはいいニュースとなったと思っています。
--
珍しいことがありました。
千葉の横田先生から電話がかかってきました。
ガヤガヤした中だったので,木更津か東京の居酒屋からと思いました。
すると突然,「隣に,懐かしい人がいる」と言ってチェンジ。
次に出た先生が,なんと新潟の太田先生。
太田先生が東京に来ているのか,横田先生が新潟に行ったのか・・・。
その太田先生から,さらに「懐かしい人が隣に・・」と出た先生は,松野先生。
なんとまあ,国語のパワフルな先生方が揃い踏みです。
新潟の国語の研究会後の2次会だそうです。
何を語らっていたのでしょうね。
横田先生の『10の力を育てる出版学習』。
こういった「形にしていく学習」は,子ども達を夢中にしますし,思わぬ力も付いてきます。
そういう光景は,本を出している先生方が出す前と出した後で,その力が違ってきている姿を見てもわかります。
アクティブラーニング時代に突入している今,こういう実践が求められています。
--
そして, 明日は大阪の上嶋先生と会います。
明日は大阪の上嶋先生と会います。
久しぶりです。
会うのは,夜の10時過ぎです。
なので,『3ステップ 聞くトレーニング』についてはあまり話ができそうにありませんが,とても楽しみです。
水曜日は,「アフリカ昼食会」です。
この間,アフリカの動きが活発なので,濃い話ができそうです。
土曜日は,チーム算数。
鹿児島の蔵満先生が参加するので,どんな話を聞けるか,楽しみです。
--
関連記事:
「チーム算数」開催日でした。
城ヶ崎先生,佐々木先生,藪田先生と私。いつものメンバーです。
基本が「話し」なので,話題はあちこちふらふらしています。
こんなので良いのだろうかと思いますが,それで良いと感じているメンバーが集まっているので,問題はありません。
今回は,珍しく,私が印刷物を2つ持って行きました。
といっても,アフリカ関係の教科書系問題です。
1つは,とっても易しい,1年生の数の問題です。
内容は易しいのですが,皆さん,ササッと問題に取り組むことができません。
すべて,ルワンダ語で書いてあるからです。
でも,しばらくすると,答えを記し始めました。
問題文を読まなくても,問題内容を見て答えることができることを,ここで体験してもらいました。
これが何を意味するかというと,「問題文を読むように」と言っても読まない子がいるのは,ごく自然の流れなのだということです。
ですので,意図的に問題文を読むようにする指導が必要になってきます。
わかりきっていても,3回読む癖をつけさせることです。
それには,テストやプリントは,「実力」の他に「慎重さ」「丁寧さ」を向上させる場であることを自覚させることです。
もう1つは,12年度のケニヤの卒業試験の問題の一部です。
こちらは全て英語です。
こちらも,やってもらいました。
こちらでは,帰国子女など,実力はあっても日本語がよくわからずにいる子の感覚を,疑似体験してもらうのがねらいでした。
単語がたった一つわからないために,とんでもない方向に答えていくことが起こります。
そうなったとしても,その子に「算数の実力」が無いとは言い切れません。
文字が読めないだけなのです。
読めない言葉があったら,「これがわからない」と指摘しても良いと言うことを教えておくことが大切なのです。
道徳の話題も出ました。
受容の話題も出ました。
師匠の話題も出ました。
どれもこれも,面白かったです。
次回は12月5日です。
鹿児島の蔵満先生が参加します。
楽しみです。
--
関連記事:
 神戸で開催された野口塾の懇親会。
神戸で開催された野口塾の懇親会。
会場の隣の場が,翌日開催される授業づくりネットワークの前夜祭の皆さんでした。
そんなことで,石川晋先生も交えて記念撮影をしました。
写真は,一番右側から,野口先生,西村先生,石川先生,私,関田先生です。
この写真,西村先生のスマホでの撮影です。
後で送ってもらうようお願いをしました。
メールでハイって届くと思っていたら,郵送で届きました。
しかも,CDに焼いてあるのみならず,プリント印刷までしてある写真まで入っていました。
CDの中を開くと,そこには,学習会の通信も一緒に入っていました。
こういう送り方をする先生ですから,学校でもさぞかしいい仕事をしているのだろうと思います。
すてきな若者と出会えました。
--
関連記事:

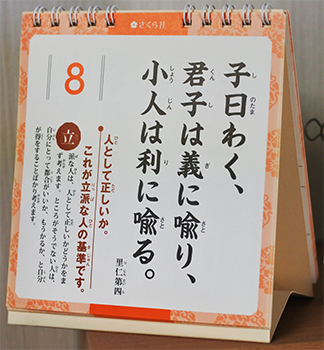







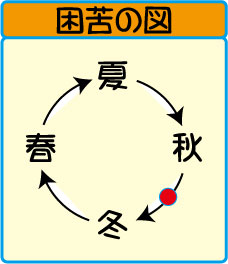
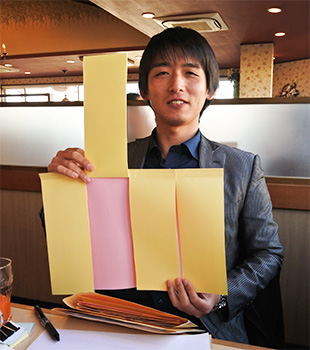
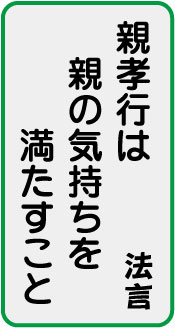




![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)














