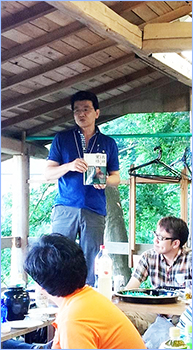 駒井先生から写真をいただきました。
駒井先生から写真をいただきました。
私が手に持っているのは,松澤先生編著の,野口先生の『教師の覚悟』です。
この本について,少し,熱く語らせていただきました。
私の隣のメガネの先生が丸岡先生です。銅像教育の第一人者です。
黄色の服の先生は,須永先生。山中先生のお弟子さんです。
須永先生は,この日,発表をしました。とても良い内容で,少し,彼に根本の話をしました。立ち話だったので,どこまで飲み込めたかは,分かりかねます。
須永先生は,月に1回,サークルを開いています。そこには,山中先生が顧問として入っています。
須永先生の実力が高いので,私もいつか1回ぐらい,顔を出してみたいと思っています。
この写真をくださった駒井先生が,一大決心をされました。
「素読については,私が本を書く。」と宣言されたのです。
松澤先生も2年前に「野口先生の伝記は私が書きます。」と宣言されました。
良い影響が出ていますね。
 このスナップは,城ヶ崎先生に撮影していただきました。
このスナップは,城ヶ崎先生に撮影していただきました。
私の隣の女性は,城ヶ崎先生のお友達です。コーチングの学習仲間だそうです。中島先生です。
バックの建物は観音堂です。これも野口家の敷地内にあります。
中島先生から,受け持っている1年生の子が,どうにも算数の文章問題がイマイチなので・・・と,文章問題への取り組み方の相談を受けました。
聞けば,文章を読まずに絵を見て答えようとするそうです。
拙い話をしました。
基本は,文章を3回読むことです。
3回繰り返し読む子は,誤読しにくいです。
授業中,良い感じで勉強していたら,100点コースになります。
ですので,3回読みたくなるように,何か,意識付けをすればいいのです。
ただ,苦手克服に取り組むときには,うんと褒められる点をまず子供達に伝えた方が良いです。それから,「3回読みにも挑戦できる子いますか」など,やる気をぴっぱる形で進めると,円滑になります。
もちろん,「条件2つを見つける」「求答を見つける」といった方法もありますが,まずは,自力で読めるようになってからです。
基本は,文章に真っ正面から向き合う子にすることです。
そこそこ納得してくれました。
 今日は,さくら社でロケでした。
今日は,さくら社でロケでした。
昼前に集合したので,お昼はみんなでロケ弁を頂きました。いつもの,栃木弁当です。
右の写真は,ロケの後半のセットです。ビデオカメラの前で,私が算数ソフトを操作しています。
こんな感じで楽しく撮影しました。
監督兼カメラの髙橋氏のアドバイスが実に良く,こうして撮影が進んでいくのかと,大変勉強になりました。
撮影されたムービーは,髙橋氏の手で編集され,ケニヤ版算数ソフトのプロモーションビデオとして仕上がります。
完成したら,ケニヤにビデオが送られ,ケニヤの研修会で放映されます。
日本にいながら,ケニヤデビューです。
もちろん,さくら社のサイトにもアップ予定です。
この年になって,こういう撮影を行え,しかも,自分も登場人物になって参加できたことが,ありがたくてなりません。
--
関連記事:
野口塾IN大阪に参加してきました。
面白かったです。
講座が終わり,最後は質疑応答。
質問の中の1つが私への質問でした。
「笑いのある楽しい話,どうやって勉強してきたのか。どんなテレビを見ているのか・・」
私の「話っぷり」というか「話術」というか,そういう所への質問でした。
 こういう質問はセミナーを終えると,よく頂いています。
こういう質問はセミナーを終えると,よく頂いています。
話の中身より,話術の方が印象深いようなのです。
その印象深い「笑いのある話」に気持ちが向くと言うことは,ご自身の授業の中に,「ビタミン笑い」が不足していたということに気づいたということなのです。
これは,「良かったジャン!」です。
今回,事務局をしてくれた阿部先生も,私の笑いを聞いて,授業に明るさを希求するようになりました。
そうしたら,子供が激変!
やる気は赤丸急上昇!
今や最高の連日になっています。
事前学習法の「バツタ」は,大ホームランだったそうで,あっという間にミラクルが起こったそうです。最高ですね!
「ビタミン笑い」は,授業という連日黙々と続く世界には必須の「知的栄養素」なのです。
感じ取った笑いは,「脳内笑いシナプス」の増加を促進し,学校大好きっ子へと子供達を変容させていくのです。
と,このぐらい,訳の分からない比喩表現を抵抗なく使えると,笑い力はアップします。
今回,御質問くださった先生は,私のことを「横山師匠」と呼んでしまうほどでした。かなり楽しかったのでしょうね。
笑いの質問を受けると,たいてい「昭和の爆笑王・林家三平師匠」の話をします。「笑いのバロメーター」の話です。
来年の冬に,どうも「笑いのある教育セミナー」が大阪で開催されるようですので,そこで,笑いのバロメーターなど,あれこれ「笑い根源の話」もできそうです。
--
野口塾での私のテーマは「算数ソフトと事前学習」でした。
どちらも,「笑い」「笑顔」が必然的に出てきます。
事前学習をしたら,その後の子供達はやる気が高まり,満足的笑顔になります。
算数ソフトを使ったら,ソフトを使うそぶりを見せただけで,笑顔が増えます。
こういう明るさのある教育,私がイチ押しする教育です。
--
写真は,叱り方の中嶋郁雄先生が撮ってくれました。ありがたいことです。
--
関連記事:
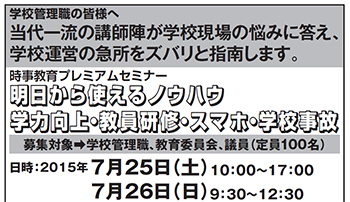 ごっついイベントがあります。
ごっついイベントがあります。
時事教育プレミアムセミナーです。
テーマが,いいですね。
「明日から使えるノウハウ
学力向上・教員研修・スマホ・学校事故」
セミナーは,7月の25日(土)と,26日(日)の両日開催されます。
学力向上,教員研修が気になるので,25日に参加する予定です。
25日には,大槻達也氏,貝ノ瀬 滋氏,近藤昭一氏の講演があります。
楽しみです。
午前中からの開催ですので,何とか朝から受講できるようにしたいと思っています。
会場は銀座です。
--
 ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。
ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。
PCというのは,日本では「パーソナルコンピュータ」といいますが,長いので「パソコン」といいます。また,「ピーシー」とも言います。
こういう略称は,ケニヤにもあり,PCは「ピースィー」だそうです。
発音の違いという程度で,なるほどと思いました。
さて,「3kg」と書いてあったら,日本では「3キログラム」と言い,略して「3キロ」です。
これが,ケニヤでは「3ケージー」なのだそうです。
頭文字で略するのです。
世界の機構などが頭文字で略されていることは知っていましたが,こういう日常語も頭文字で略しているようです。
国際化がどんどん進んだら,国際派の先生も増えていき,国際的な略称も教える先生が出てくるかも知れませんね。
--
明後日は,大阪の野口塾です。
中嶋先生の講座もあり,賑やかな一日になりそうで,今から楽しみです。
--
写真は,大船の観音様。駅からつながっている歩道橋から見えます。いいお顔ですね。しばし,拝みました。
--
関連記事:
教えてくれたのは,実力者の浅村先生です。
学力向上指導教員が6年生の授業を参加したそうです。
その時,6年生の先生は,浅村先生に勧められて,この円を転がす算数ソフトを使いました。
そうしたら,指導教員から「ソフトがいい」と褒められたそうです。
もちろん,指導された先生の指導力も褒められていますが,ソフトも褒められ,とても嬉しい気持ちになりました。
--
少々,このソフトについて,お話をしましょう。
「円周率」を学ぶ場面で使うソフトです。
円周率は3.14と覚えてしまえば,それで良いのかも知れません。でも,小学校は,そんな暗記ですますようなことはしません。
1,どうして「3.14」になるのか。
2,「3.14」とは何と何の関係のことか。
こういう大事な思考の学習を,しっかり学習します。
授業では,円を転がして「直径」と「円周」の関係を学びます。
工作用紙に描いた円を切り抜いて,実際に転がして・・・と授業をします。
ところが,人力ですので,どうしても誤差が出ます。
また,実際に転がす操作をするので,転がすところにエネルギーがそそられ,「直径」の数値と,「円周」数値とを見比べて考えるという,一番大事なところに力が入りにくくなります。
このソフト。転がる様子を見ることができるので,ちょっと俯瞰して概念を把握できます。
さらに,ボタンをクリックすると,物差しに直径で幾つ分になるのか,示されます。
1cmの円でも,2cmの円でも・・・・10cmの円でも,どれも「直径が3つとちょっと」になることを見ることができます。
10個もある円で,いつでも3.14になっていることを確かめたら,円周率というのは,「直径と円周の関係」であり,「どの円でも直径の3.14倍が円周!」と伝わってきますね。
浅村先生からのお知らせメールで,とても元気を頂きました。
算数ソフト,これからも,少しずつですが,紹介していきます。楽しいですね。
--
関連記事:
今度の土曜日は,大阪の「授業道場野口塾IN大阪」に参加します。
私も一こまお話をします。
「最先端!算数ソフトと事前学習」です。
--
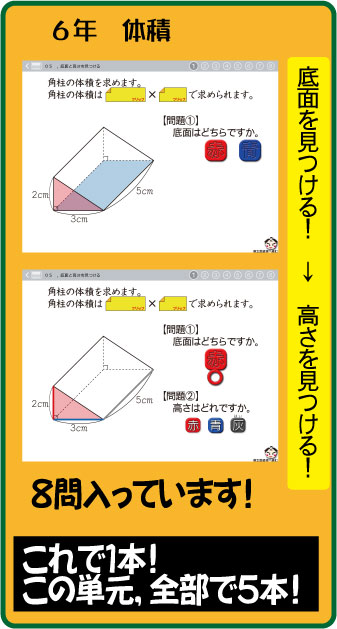 算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。
算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。
6年生の「体積」から1本,ご紹介します。
体積の求め方として,「底面積×高さ」を学習します。
この考え方はとてもありがたい表現です。
なにしろ,底面の形がどう変わろうと,すべて「底面積×高さ」と表現できます。
柱状の立体なら,どんな形をしていても,「底面積×高さ」なのです。なので,「公式」となっています。
たいへん,ありがたい公式なのですが,立体を見て底面がどこなのか,正しく指摘できな子もいます。
これは,立体の底面を見つける経験が不足しているだけのことです。
もし,底面を間違えそうな子がいたら,「05 ,底面と高さを見つける」のソフトを使ってみてください。
立体の見取り図を見ながら,
「底面を見つける」→「高さを見つける」
この学習を8問も連続してできます。
8問も練習をしたら,立体の底面を見分ける目ができてきます。
--
この「底面積×高さ」は,中学へ進むと「V=Sh」と横文字になります。
非常に簡略になるので,図を書いても文字がじゃまになりません。
こういう点では,アルファベットはシンプルでいいと思っています。
このVは,ボリューム。volume。
Sは,サーフェイス。Surface。
hは,ハイ。Height。
マイクロソフトが作った薄型のPCの名前がサーフェイスだったので,このSが少し日本語化し,意味を理解しやすくなりました。
6年生での学習では,時々,「中学へ行くと・・・」と話をするのもいいです。
--
関連記事:

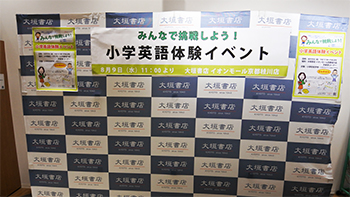




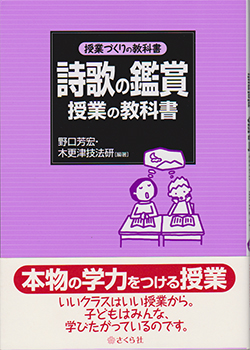

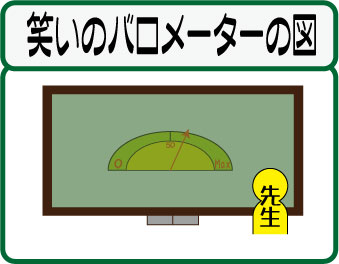
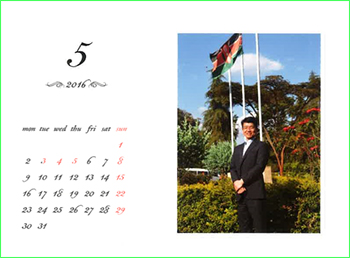
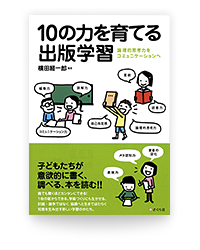


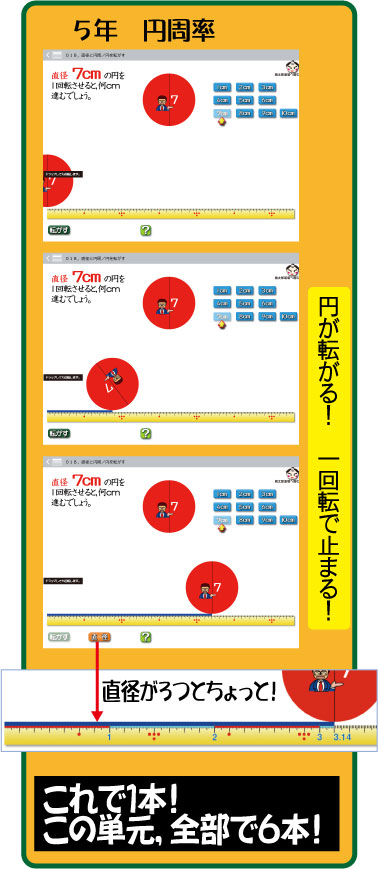



![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)















